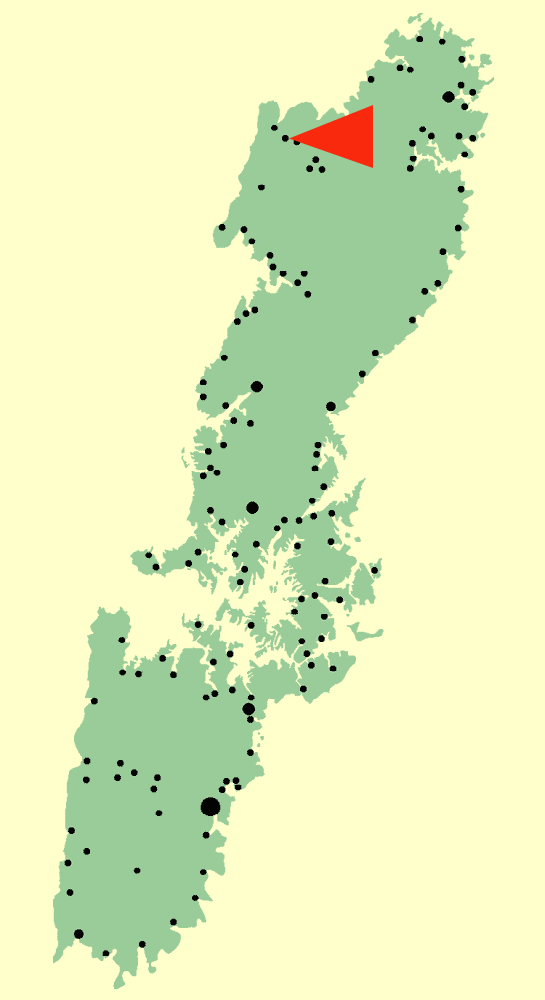2025年6月23日更新

上県町
友谷
【ともや】
江戸時代の干拓によって
生まれた農地「友谷原」は
佐護米の主要生産地
一番海に近い佐護平野、友谷原
「対馬最大の穀倉地帯、佐護平野」という表現をよく目にする。そして、その成り立ちとして、佐護川の自由蛇行(洪水のたびごとに流路の位置を変え得るような状態にある場合の蛇行)によって形成された沖積平野という説明が多いが、実際は中世から近世にかけて広い河原を干拓などによって耕地化し、それによって生まれた小さな平野の連なりをまとめて佐護平野と表現している。つまり、佐護平野は、自然と佐護の人たちの手によって作られた地形という理解が正しいのではないだろうか。
そんな小さな平野の連なりの中で最も知られているのが、対馬一の美田とも紹介されている「友谷原」。友谷集落の西側、佐護川の向こうに広がる水田地帯だ。対馬では知らない人はいない「佐護米」の主要産地でもある。

Google Earthで北から俯瞰した佐護平野 出典:Google Earth(地名を追加記入)

佐護周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大/施設名追加等)、長崎県遺跡地図
少し下流に弥生時代の人の営み
佐護の他の集落と同じように、友谷周辺も遺跡が多い。
佐護で最も古い遺跡と言われているのが、縄文晩期の黒曜石製遺物が見つかった「コウブリヤ洞穴」。佐護川河口右岸の山林の中にあり(上の佐護周辺地図参照)、佐護では縄文唯一の遺跡だ。そこからは古墳時代の須恵器片も出土している。
弥生以後の遺跡は多く、銅矛が見つかった「ヒツ原(坂尻)遺跡」は弥生時代の遺物包含地と推定され、神御魂神社の境内を含む一帯「小坂遺跡」からは古墳時代の陶質土器が出土した。この佐護川河口に近い右岸に弥生時代後期から人の営みがあり、それが友谷集落の形成につながったと考えられている。
また、友谷集落内の山際にある「ゴンクマ遺跡」や、集落の南端にある「クビル遺跡」は弥生時代から古墳時代の墳墓遺跡と推定されている。弥生時代の墳墓は村の外、海側に作る場合がほとんどであり、、それらの遺跡はおそらく井口集落に関係する遺跡と考えられ、弥生時代や古墳時代には現在の友谷集落の辺りはまだ佐護川河川敷で、人は住んでいなかったと考えてよさそうだ。
坂尻周辺が古友谷とも言われているように、かつて友谷の人たちの先祖は坂尻あたりに住み、狭い土地を耕しながら海の幸と山の幸も加え、暮らしを維持してきたのではないだろうか。

友谷周辺地図: 出典:国土地理院地形図(地名拡大・施設名追加等)、長崎県遺跡地図
弥生時代に渡来人が大量移住⁉
佐護に限らず対馬で弥生時代の遺跡が多いのは、弥生以後、日本の人口が爆発的に増えていったことと関係している。その遠因として地球の寒冷化があげられているが、寒冷化が引き金になって大陸で土地の奪い合いなどが起こり、その戦いからの敗走、あるいはそれを避けるために、多くの人々が新天地をめざして海を渡った。
日本の縄文末期の人口は8万人、弥生末期の人口は60万人というのが定説として広く認められており、それに弥生時代を1000年とし、1年間の人口増加率を0.1%として計算すると、弥生時代1000年間で渡来要因によって増えた人口は38万3千人となる。人口全体の63.8%が渡来人の移住によって増えたことになる。
つまり、それ程多くの人が弥生時代(おそらく中期以後)に大陸から日本に押し寄せ、その途中過程で対馬に住みついたのが対馬人の先祖と考えてよさそうだ。民族もさまざまなら言葉もさまざまだったのではないだろうか。
佐護を選んだグループは、三根や仁位の一団ほど大きな集団ではなかったようだが、佐護川河畔の平らな土地を耕し、多くは麦を育て、村を築いた。その中の一つがヒツ原・坂尻辺りにあったようだ。
軍備壇遺跡、北の守りの最前線か
千俵蒔山とガウジ岳の間の稜線西側には、杉林の中に石積みが数カ所あり、平安時代に築かれた防塁の跡、あるいは城館跡と考えられており、「軍備壇遺跡」と命名されている。(佐護周辺地図参照)
平安時代の外寇といえば、被害の大きかったのが1019年(寛仁3年)の「刀伊の入寇」であり、さらに9世紀から10世紀前半にかけて頻繁に襲ってきた新羅船による海賊行為が挙げられる。これらの防塁はそれらから対馬や日本国を守るために造られたものだろうか。
遺跡地図には掲載されていないが、ガウジ岳の南側(友谷側)にも石積みがあるという。
鎌倉時代の塩田は「えんでん」にあらず
鎌倉時代初期の1228年(安貞2年)の文書に、佐護の塩田4段(4,800㎡)に関する訴訟について書かれたものがあり、それはかつて「塩田原(しおたばる)」と呼ばれ、現在では対馬随一の美田と評される「友谷原(ともやばる)」のことと言われている。
「塩田」というと製塩のための田と思われがちだが、一般的に塩を作るために整地した砂地を「塩田(しおた)」と表現するようになったのは明治以後と言われており、それ以前は「塩浜」と表現した。佐護の「塩田4段」は「塩気を含んだ畑4反」の意味だったと考えられる。
現在、佐護西里に「塩田」 「上塩田」という小字があり、現在は佐護川左岸になっているが、その辺りが鎌倉時代の塩田訴訟の当該地、かつての塩田の名残ではないだろうか。
友谷原は直線道路より北側だけで約16万㎡あり、「塩田4段」の4段は4,800㎡だから、その約30分の1。小字の土地の広さもほぼこのくらいのようだ。

7月の友谷原
田代領からの入植者
友谷には対馬では珍しい名字「春日亀(かすがめ)」の家が5軒ある(2004年時点)。江戸時代に九州の田代領から招かれた農師(農業指導者)の子孫だそうだが、いつ頃友谷に入ったかを伝える記録はまだ見つかっていない。
『新対馬島誌』(1964年)には「(享保の頃に)仁位浜の開田に招いた田代の農師を佐護に移して田作りの農師に立てなければならない実情であった」とあるが、『豊玉町誌』(1992年)によると、仁位浜に招いた2家族のうちの1家族は田代に戻り、別の家族は仁位に残っている。(本来は佐護と仁田で指導させるために招いたが、当時藩営で干拓されたばかりの仁位浜が優先された)
また、1727年(享保12年)、仁位浜の開田と田作り指導が一段落したからだだろう、御郡支配が田代の農師を佐護に移すことを佐護の奉役に提案したところ、二人の奉役が断ってきたそうだ。
その後、田作り(稲作)のメリットを佐護の人たちに伝える機会を設けたようだが、すぐに稲作を始めたという記録はない。年貢を納める農民にとってどれだけのメリットがあるのか疑問ではあるし、保守的な農民を動かすのに時間を要したことは想像に難くない。田代から農師を呼ぶまでどのくらい掛かったただろうか。1700年代半ばくらいには入植していたかも知れない。
1832年(天保3年)、阿連村の足軽の父親が佐護に田作り指南として入ったという記録があり、かなりの成果を上げたそうだ。田代から農師は入ったものの、なかなか普及しなかったので、藩がテコ入れしたということだろうか。
その後、友谷は井口とともに佐護の稲作の中心地となり、昭和になってポンプで水利を改善した他の佐護の村々とともに、対馬では数少ない米の一大供給地となっている。
江戸時代、すでに対馬の穀倉地帯として
そんな江戸時代の友谷の人たちの暮らしを食糧事情の視点から見てみたい。
1700年(元禄13年)は人口データが不記載のため、一人がたべる米麦の量を求めるのに、1戸当たりの人数を1861年と同等と仮定すると、人口は136人となる。それで計算すると、一人当たり1年で1.23石、1日3.3合と、その頃の対馬の平均、0.48石ならびに1.3合を大きく上回る。もちろん当時の主食は大麦だった。
1861年(文久元年)には、米麦の収穫量は1.14倍に増え、一人当たり1年1.29石、1日3.5合と、当時の対馬の平均1年0.66合、1日1.8合の2倍の数字になる。
収穫量の増加は1.14倍だが、麦から米への切り替え等もあったから、食糧事情としては数字以上に変化があったと推測できる。また、馬の頭数が増えたのは木庭作も増え、そこに孝行芋を植えたと考えられる。
対馬の郷村としてはまだ余裕のある暮らしが展開されていたのではないだろうか。
1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』
物成約116石、戸数30、人口 ヌケ、神社1、寺0、給人4、公役人19、肝煎1、猟師14、牛35、馬21、船0
1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』
籾麦529石、家30、人口136、男57、女58、10歳以下21、牛25、馬34、孝行芋1,250俵
※対馬藩の「物成(年貢)」は収穫量の1/4だが、それ以外に金銭で納める税金「公役銀」を工面するために麦などを売る必要があり、その他の支出も考慮すると、食糧として農民に残るのは収穫量の1/3くらいと考えられている。村によって多少事情が異なるのであくまでも計算値、目安と理解してほしい。

春の友谷集落と佐護川
友谷原は友谷だけの農地ではない
現在は「友谷原(ともやばる)」と呼ばれているが、かつては「塩田原(しおだばる)」と呼ばれ、地元では「原」を略して「塩田(しおだ)」と呼ばれたそうだ。
江戸時代に大々的な干拓は行われたものの、長い間、道も土手も低く、海水が田に流れ込むこともあった。そのため麦は植えられなかったと言う。それが「塩田」だ。
前述の鎌倉時代の塩田訴訟の田(稲作の田ではない)は、広い河原に土を入れ周囲を石垣で囲っただけの畑だったのではないだろうか。時代とともに徐々に改良され塩害は抑えられ、稲作が普及し、昭和になって二毛作も行われるようになった。
友谷原には、深山、井口、恵古など、佐護中から耕作に来たそうだ。自作地の足りない湊の人たちは、深山、恵古の人の田を小作したという。それが、1946年の農地改革で小作人に譲渡に近い価格で売り渡されることになり、湊の人たちの所有地が一挙に増えることになった。実際に友谷原で会う人は湊の人たちが多い。
佐護平野の農地基盤整備事業が1986年(昭和61年)から進められ、1999年(平成11年)に完成。総面積79.6ヘクタール、受益戸数185戸と言われている。その4割を占める約33ヘクタールが友谷原で、大岩橋の北詰に「佐護地区土地改良記念の碑」が建てられている。
なお、友谷原をまっすぐに突っ切る直線道路は、棹崎砲台のために造られた軍道で、対馬では珍しい整然とした田園風景に一役買っている。

友谷原と佐護川と、まっすぐ延びる元軍道

大岩橋北詰に建てられた「佐護地区土地改良記念の碑」
天道法師の母神とされる、神御魂神社
佐護川河口の右岸に建てられた神御魂神社(かんむすびじんじゃ)は、明治の初めごろ、神社制度の見直しによって友谷の氏神となったが、それ以前は湊の氏神だった。
祭神は神皇産霊尊(かんむすびのみこと)。日本神話で神皇産霊尊を女神、高皇産霊尊(たかみむすびのみこと)を男神としてセットで語られる説もあり、対馬でも二神の間に生まれたのが天道法師(多久頭魂)とされている。対岸である湊側にある天神多久頭魂神社の母神ということになる。
前述のように境内とその周辺は、小坂遺跡となっており、陶質土器(古墳時代)が出土した。さらに『島の故事探索(四)』によると黒曜石も採集されたというから、弥生時代から人の営みがあったのかも知れない。

神御魂神社

神御魂神社前に建てられた開墾紀念碑:大正元年と刻まれている
その他
◎大塔持ち:陸良親王(おきながしんのう)が対馬に逃れ大塔備前守を名乗ったと言われているが、正平の頃(1346年~1370年)に、その長子 大塔茂景の知行地が佐護川河口付近の海岸、地名も「大塔持ち」となった土地がある(現在、字名としてはない)。海に面しており耕作には不向きであるところから、おそらく塩づくり経営の権利を知行としたのではないだろうか。(陸良親王については「根緒」のページで詳しく触れている)
◎火鎮神社(ほのかみじんじゃ):明治初期に神御魂神社が友谷の氏神とされるまでは、こちらが友谷の氏神だった。友谷の公民館横にあり、昔は女房神の社があったという。社名から「火を鎮める」→「火事から村を守る」神様という性格(役割)を与えられているが、佐護の郷土史家は、本来は江戸時代の記録にある「こけのごおう社」ではないかという説を唱えている。午王社は志多留(五王神社)にもあり、祭神は素戔嗚尊だ。
【地名の由来】 「苫屋(とまや)」が転じて。かつてこの地に何らかの目的で苫屋が建てられていたか。
Ⓒ対馬全カタログ