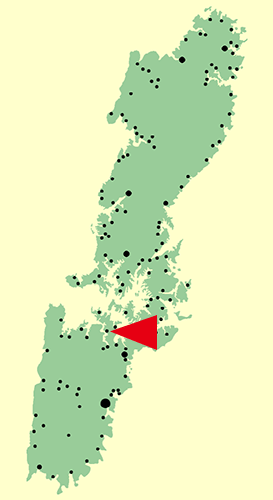2025年6月23日更新

美津島町
黒瀬
【くろせ】
金田城あっての黑瀨、
黑瀨あっての金田城。
小村にして大役を担う
集落の狭さでは対馬一!?
黑瀨集落は家が密集し、さらに狭い。江戸時代と現代と少なくとも2度の埋め立てを経ており、それ以前は猫の額と形容できるような狭小地だったはずだ。
下の写真を見てわかるように、黑瀨には作物を育てる土地がほとんどない。自給自足の時代なら、誰も好んで住みたいとは思わないだろう。そんな土地がどうして村を形成するに到ったか。それはここに住まわなければならない理由と、平地に縛られない農業があったからではないだろうか。
まず、平地に縛られない農業だが、山を畑にする焼畑農業がそれに当たる。対馬風に言えば「木庭作」だ。
焼畑が対馬に入ってきたのは弥生時代から古代にかけてと考えられており、黑瀨が誕生する頃には普通に使える農業技術になっていたはず。木庭作あっての黑瀨だった。

今も狭い黑瀨集落(2022年)

黒瀬周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大、施設名追加、旧道追加等)、長崎県遺跡地図
金田城の築城、運営に貢献か
別アプローチから黑瀨集落の誕生を考察しようとすると、つまり「ここに住まわなければいけない理由」から解き明かそうとすると 『美津島町誌』にヒントが書かれてあった。
『美津島町誌』の黑瀨村の項に、『津島紀事』によれば室町幕府創設に貢献し、恩賞の一部として改めて対馬国の守護職となった武藤頼尚(むとうよりひさ)から城山守護職に任命されたというのが黑瀨村の住人・平山権太夫だったという件(くだり)があり、その任命は「旧例によって」と書かれている。武藤頼尚が対馬守護職になった1336年よりもかなり前から平山家が城山を守ってきたことが窺える。
また、金田城の守護神でもある大吉戸神社は黑瀨の氏神でもあり、境内・社の清掃や祭祀に奉仕してきたのが黑瀨の人々だった。
ここから、黑瀨は他の村にはない金田城との密接な関係を有し、それは築城の頃からではないかと考えられる。造成や維持のために物資や人員(工夫や防人など)の補給路が必要だが、黑瀨がその役割を担っていたのではないだろうか。

黒瀬から金田城(城山)を望む
仮説:黑瀨は金田城の入口として発展!?
金田城築城時、対馬の中心は鶏知だった。九州からの船は鶏知に着き、鶏知から城山まで人や物を運ばなければならなかった。そこで最適なルートが検討されたはずだ。
おそらく、人の場合は陸路で黑瀨まで行き、船に乗り換え城山の海岸に上陸。物資の場合、鶏知最寄りの港である樽ヶ浜まで運び、船で竹敷の島之内へ。そこから山越えで黑瀨、そして黑瀨から城山の海岸まで船で運搬したのではないだろうか。(山越えの旧道をかつての山道と推測し、「黑瀨周辺地図」に表示)
湾を横断すると城山側までは約1km、手漕ぎ船で10分ほどしか掛からない。そこまでの陸路はできるだけ高低差の少ないところを選び道もつくっただろうし、簡易的な船着場もつくったはずだ。そして、その船着場が黑瀨の起こりではないだろうか。
また、金田城築城の目的を、当時鶏知に住んでいた国司、郡司などの重要人物およびその周辺の人たちを城内に避難させて、籠城(ろうじょう)戦を戦い抜くためとする説もある。その場合、黑瀨はその避難の中継地であり、かなり重要な役割を担っていたと言える。常に数艘の船が係留されていたと考えていいのではないだろうか。
金田城が役割を終えるのは、10世紀になって武士団が台頭し防人制がなくなってから。その頃には黑瀨も村に相応しい集落になっていたのではないだろうか。もしかすると、防人の中には家族をつくり黑瀨に住んだ人間がいたかも知れない。
古代、中世の黑瀨に関しては、武藤頼尚と平山権太夫の話以外に情報がなく、そこを頼りに仮説を立ててみたがどうだろう。
黑瀨遺跡の謎
黑瀨周辺には2つの遺跡がある。洲藻寄りの「皇后崎第1遺跡」では、箱式石棺数基が発見され、弥生から古墳時代前期のものと推定された。しかし、これは洲藻に拠点がある豪族のものと考えられ、黑瀨に関連づけるのは難しい。
もっと黑瀨に近い 「黑瀨遺跡」はどうだろう。発見されたのは箱式石棺と書かれているだけだが、入江の奥の、かつては岬だっただろうと考えられる丘の上にある。時代は弥生~古墳時代だそうだ。
黑瀨湾から大きく凹んだところにあるから、洲藻の関係者とは考えにくい。もしかするとこの付近に村があったのかも知れない。それが黑瀨の前身の村なのかも知れない。村がなくても築城当初は、遺跡付近の海岸から城山に物資を供給していたのかも知れない。
「地面三合、海漁七合」の教え
江戸時代後期の対馬藩士の書『楽郊紀聞』に、黒瀬では昔から「地面三合、海漁七合」という言葉で海漁の大切さを戒めていると、書かれている。海漁(採藻や鰯漁)なければ、田畑に肥料が与えられず、地味が悪ければ作物が育たない。もっとも話だ、と。
戒めとしては対馬全島に当てはまる内容だが、それが言葉となり子々孫々受け継がれていることが重要だ。その理由は、耕作地の少ない黑瀨だからこそではないだろうか。耕作地が少ないということは収穫量が少ない、食糧が少ないということだ。
1700年(元禄13年)の黑瀨村のデータをもとに村人一人(10歳以上)当たりの食糧(麦)を計算すると、1年間に0.24石、1日0.66合。当時の対馬の平均の半分だ。
その約160年後となる1861年(文久元年)には、収穫量は増えたものの人口も増えたので、一人当たり(11歳以上で計算)1年間0.25石、1日0.7合となり、当時の対馬の平均の4割と、さらに減っている。(ただし孝行芋が減少分をカバーしたはずだ)
その麦の不足量を補ったのが海の恵み。地先の黑瀨湾だけでなく、浦奥の洲藻浦の漁業権も黑瀨にあり、湾内で取った魚や貝や海草は、すべて黑瀨のものとなった。それは肥料にもなるが、その前に人々の空腹を満たす食糧となった。
「地面三合、海漁七合」は戒めでもありながら、黑瀨の食糧の実態でもあり、農業より漁業の比重が大きく、海に頼っていたことの証左とは考えられないだろうか。
1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』
物成約19石、戸数26、人口(10歳以上)105、神社1、寺1、給人0、公役人13、肝煎1、猟師0、牛0、馬0、船
1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』
籾麦94石、家25、人口132、男55、女67、10歳以下10、牛17、馬0、孝行芋1,920俵
※対馬藩の「物成(年貢)」は収穫量の1/4だが、それ以外に金銭で納める税金「公役銀」を工面するために麦などを売る必要があり、その他の支出も考慮すると、食糧として農民に残るのは収穫量の1/3くらいと考えられている。村によって多少事情が異なるのであくまでも計算値、目安と理解してほしい。
幕末の大事件、ロシア艦の不法占拠対応の拠点に
1861年(文久元年)2月、ロシア軍船・ポサドニック号が浅茅湾に入り、湾内での船の修理を申し出た。1カ月後にはポサドニック号は湾内を航行したあと、強引に芋崎浦の「大瀬の浜」に停泊。上陸して小屋を建て、井戸を掘り、最後は土地租借を申し入れてきた。
この一大事を収めるべく藩は家老の仁位孫一郎を黑瀨に派遣し、ロシアとの交渉の指揮をとらせた。旅宿に滞在しながら、ポサドニック号に出向いたり、ある時は相手の艦長を宿に招いたり、また藩の意向を確認する必要があれば夜のうちに府中に戻り、翌日藩邸に報告に上がる等、忙しく動いたようだ。
移動時間を考えると、おそらく馬を使ったと考えられ、幕末期には府中から黑瀨付近まで馬を走らすことのできる道が通っていたと推測できる。芋崎に近いだけでなく、府中との連絡が迅速に行えることも黑瀨をロシア対応の拠点に選んだ理由だろう。
最後は幕府とロシアの間で交渉が行われ、8月15日にポサドニックは半年ぶりに浅茅湾を出ていくことになるのだが、対馬が占領されるかも知れないという一大危機だった。その間、黑瀨は、ロシアとの交渉の前線基地として不安と緊張の日々だったに違いない。

浅茅湾地形図 出典:国土地理院地形図(地名拡大、名所追加・地名削除等)
国指定重要文化財の「銅造如来坐像」
現在、黑瀨で最も有名なものといえば、国指定重要文化財「銅造如来坐像」だろう。1977年(昭和52年)に黒瀬で発見され、黑瀨では安産の女神(おんながみ)=観音様として信仰を集めている。
8世紀に新羅で鋳造されたといわれ、高さは46.7cm。胴体や座面に火災による大きな損傷があるものの、当時の新羅製の仏像としては最大のものと言われている。どのような経緯で黒瀬に来たのかは不明だそうだ。
顔立ちの優雅さといい、新羅統一時代の仏像としては最も優れた作品の一つと評価が高く、1982年(昭和57年)に奈良で開催された「百済新羅の金銅仏―飛鳥白鳳仏の源流」にも出展された。
黑瀨にはもう一体仏像がある。14世紀後半に韓国で製作されたとされる菩薩像で、火災によって胴体や台座の一部が溶けている。こちらの像は新羅仏と対比し、男神(おとこがみ)とされている。
二つの仏像はコンクリート造の黑瀨観音堂に安置され、通常は施錠されているが、対馬市に問い合わせれば拝観は可能だそうだ。

国指定重要文化財の銅造如来坐像(左)と銅造菩薩坐像(右)
半島全体が遺跡、金田城跡
城山は西側の斜面を除いてほとんどが、黑瀨の村域となっている。江戸時代であれば、黑瀨村の領地ということになる。それは、黒瀬の人々が金田城の城守りを任せられ、城の守護神である大吉戸神社の祭祀に奉仕してきたことにつながる。
前述の『楽郊紀聞』には、藩が大吉戸神社の神祭料を黒瀬村に払い、黒瀬村は麦を上納したと書かれている。江戸時代、大吉戸神社は「城八幡宮」「黒瀬八幡」などと呼ばれたそうだ。
また、金田城跡は国特別史跡に指定されており、石塁、掘立柱建物跡、炉跡、城門跡、門礎石などを山を巡りながら探索することができる。

金田城・東南角石塁から黑瀨湾を望む
対馬のヒオウギ貝養殖の発祥地
江戸時代、黑瀨は竹敷・濃部・大船越・久須保・緒方とともに、城の台所に浅茅湾でとれた魚や貝を納める「御菜浦(魚菜村)」六ヵ村の一つだった。昔から黑瀨湾はプランクトンの豊富な、魚や貝たちにとって栄養豊かな海として知られていたそうだ。
そして現在、黑瀨湾ではヒオウギ貝の養殖が行われている。ヒオウギ貝は、東海岸でも養殖されているが、対馬のヒオウギ貝の歴史は黑瀨から始まった。
対馬に適した新たな漁業の開発をめざして、大分県などで修業し、ヒオウギ貝の養殖を学んだ黑瀨出身の漁業者が、1960年頃に黑瀨湾で養殖を開始。そこから浅茅湾、三浦湾を中心に広がった。
黑瀨湾で育ったヒオウギ貝は「太い」と、地元の養殖者は自慢する。やはり黑瀨湾はプランクトンが多いからだそうだ。

軒下にヒオウギ貝の絵看板
【地名の由来】 かつて部落の前の浦に黒色の岩瀬があったからと言われている。
Ⓒ対馬全カタログ