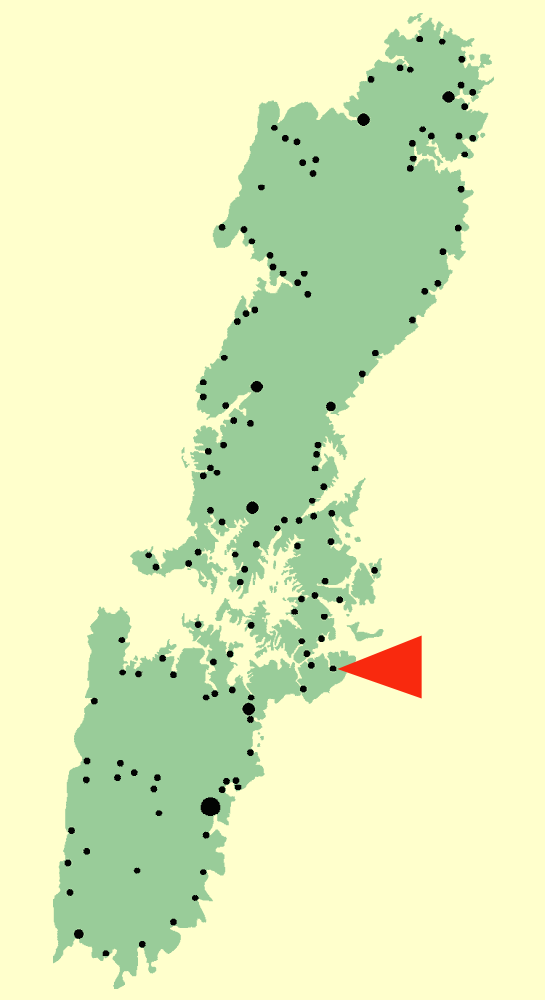2023年7月21日

美津島町
緒方
【おかた】
左右対称の美しい村には
弥生の頃から営みと
協力し合う気風があった
風景が気に入ったのも、ここに住み始めた理由の1つか
浦奥の金毘羅山を硯屏にした硯のような緒方浦。ここまでの左右対称の美しい村は、対馬ではここしかない。港湾整備で左右対称になったとはいえ、浦奥に金毘羅山をいただく景色は、何千年も前から変わることのないこの浦の魅力であったに違いない。
浦口東岸のわしのす鼻で3基の石棺が発見され(わしのす鼻遺跡)、弥生時代終末期の大型壺の破片が出土していることから、緒方は弥生時代以前からの村と考えられている。
さらに、浦の中程の東岸から3基の石棺が見つかり、ガラス玉や壺の一部が発見され(緒方浦遺跡)、その後の調査で緒方浦で計8カ所の遺跡が確認された。
ここに村をつくろうと決めた最初の弥生人たちにとっても、この浦の風景は心地よいものだったものではないだろうか。

緒方周辺地形図:緒方浦東岸は出入りが多く、埋葬に最適な場所が多いことも、墳墓遺跡が多い理由のひとつではないだろうか 出典:国土地理院地形図(地名拡大、地名・遺跡追加等)

烏帽子岳展望台から眺める紺青岳(中央の山)。その左が明神岳、さらにその左の台形に見える山が金毘羅山。左手前の大きな山が浅茅山
協力し合う気風
室町時代中期の朝鮮の書『海東諸国紀』には、緒方浦は20余戸と書かれてある。ちなみに隣の久須保も20余戸。どちらも比較的小さな村だったということだ。
乙宮神社があるところから、そこはかつては塩竈神社で、室町時代は緒方にも塩竃があり、塩づくりをメインの産業にしていたのではないだろうか。
江戸時代の統計で侍(給人・足軽)がいない、つまり土着の武士がいない村だったことを考慮すると、昔から村を支配する者がなく、リーダーはいたかも知れないが、皆で力を合わせ地味にコツコツやってきた村、と考えてよさそうだ。
江戸時代に入り、対馬藩が誕生すると、府中(元厳原市街)に近い村6村が御菜村(魚菜村)に指定され、公役のかわりに魚と馬草を上納した。
緒方も根緒、久須保、大船越、濃部、竹敷、黒瀬と同じく御菜村に指定されたのだが、これにも全員が協力して対応したのではないだろうか。

緒方の乙宮神社:乙宮神社祭りは、1月・6月・11月の17日の3回。かつては法者を呼び祈祷をしてもらったそうだ。境内の形が緒方浦に似ている
公役人の多い村
『美津島町誌』に「資料によると、緒方には・・給人家はいなく、本百姓のみの本戸部落」と書かれてある。その資料とは1700年(元禄13年)に幕府に提出した『元禄郷村帳』だろうか。このような項目・数字が並んでいる。
物成(年貢)約20石、戸数25、人口110、神社1、寺1、給人0、公役人20、肝煎1、猟師4、牛2、馬1、船9
この中で注目すべき数字は「公役人20」だ。戸数25には、神社、寺、隠居した夫婦の家も含まれるだろうから、実際は20家族くらいだろう。だから家を代表する全員が公役人と考えてよさそうだ。
こういう村は、対馬では極めて珍しい。元禄時代に給人・足軽のいない村は25村あったが、ここまで公役人の割合が多いのは南室(11戸中9戸が公役人)と緒方くらいだ。
厳しかった食状況
もう一つ注目すべき数字が「物成(年貢)約20石」。当時の対馬では年貢は25%だったから、生産高は80石となり、自分たちで食べる米麦は60石となる。
人口110人で一人当たりを計算すると60石÷110となり、一人当たり0.54石。対馬の郷村平均は一人当たり1.1石だから、緒方の人たちの米麦を食する量は、平均の半分となる。(この統計には10歳以下の子供は含まれないので、実際はさらに数値が下がる)
この状況は160年後も変わらなかったようだ。1861年(文久元年)に幕府の役人がまとめた統計『八郷村々惣出来高等調帳』は、少し項目は違うがこの村の食糧事情の厳しさを表わしている。
籾麦93石、家22、人口129、男52、女48、10歳以下29、牛16、馬6、孝行芋400俵
元禄のデータと揃えるために11歳以上の人口100人で計算すると、一人当たり米麦は0.7石(子供も含めると0.54石)。サツマイモ(対馬では孝行芋という)400俵も加わり、改善はされたが厳しい食状況だった。
但し、江戸末期になっても給人はおらず、貧富の差も少なく、食料も農民が収獲に応じて得ることができた。そう考えると、他の村の農民に比べて生活がたいへんだったと単純には言えない。
給人不在の唯一のデメリットか?
江戸時代中期は対馬では開き(干拓)が奨励された時代だった。さまざまな村で開きが行われたが、そのほとんどが給人や足軽によるものだった。やりたくても暮らしに余裕がなければ、完遂できない。
給人や足軽のいない村でも開きは行われたが、小規模のものだったようだ。緒方で大幅な開田が行われなかったのも、給人不在が理由の一つだったのでないだろうか。
明治時代に誕生した、村独自の憲法「緒方憲法」
村の決まり事を成文化した“村規約”は色々な村にある、あるいはあったようだ。『美津島の自然と文化(三)』によると、1985年(昭和60年)頃には、美津島町エリアだけでも、濃部、賀谷、鴨居瀬、大山、緒方、洲藻、尾崎にはあったそうだ。この7つの村の特徴は多様だから、規約の成立過程もさまざまではないだろうか。
「緒方憲法」と呼ばれる緒方の村規約がはじめて成文化されたのが、1910年(明治43年)5月13日。村の年中行事や共同事業に対する慣習や取り決めがメインで、“憲法”という程たいそうなものではないそうだ。おそらく成文化以前、江戸時代にも取り決めは存在し、それをより確実なものにするために紙に記したということだろう。
時代に合わせて変わっていく村規約
毎年3月に村の総会が開催され、規約は2年に1回見直すことになっている。以前は行事に出なければ違約金を徴収するという方法を採っていたが、現在は勤め人でも参加しやすいように行事日程を日曜日にずらす等、柔軟な方向に変わってきているという
給人が不在だったからこそ、取り決めが重要だったとも考えられる。協力し合うにはどうすればよいか、継続させるにはどうすればよいか。それぞれの時代に相応しい知恵が反映されてきたのだろう。
なお、総会に出席できるのは69歳まで。70歳になると引退だそうだ。ちなみに2023年は現役人数は32名。高齢化が進む昨今、見直しが必要ではないかいう高齢者の意見もある。
嶽神様詣りなど、伝統行事の残存地区
「緒方憲法」と呼ばれた村規約のおかげで、緒方では行事が廃れることが少なかったようだ。
金比羅詣りが旧の3月10日と10月10日。嶽神様詣りが旧の6月1日と8月1日に行われる。
嶽神様詣りは、金比羅山の南の中岳頂上(標高約130m)にある嶽神様の社に詣る行事で、行事前日に神主とその年の役の人間が登って、皆が登りやすいように道をさらえ、当日は20名ほどがお詣りするそうだ。
旧暦の9月に「お出ませ」、11月に「お入りませ」という行事もある。氏神様が出雲に出かけるから「お出ませ」、帰ってくるから「お入りませ」。「お出ませ」は村によっては「お出船」とも呼ばれた。「お入りませ」では、氏神様(緒方では乙宮神社)の社に「おこもり」をして神様を迎えたそうだ。
盆踊りは緒方にはない。盆には「願ほどき」と「願掛け」が行われたそうだが、こちらは何十年か前になくなったそうだ。

嶽神様の祠
篤い弘法大師信仰
緒方は久須保と同じように弘法大師信仰の篤い地区だ。大師堂は、月光山直観寺というお寺で、対馬四国八十八カ所参りの58番札所になっている。
3月21日の祭日には周辺を掃除し、酒肴を持ち寄り、地区の皆で盛り上がる。かつては月の21日に女だけが集まり飲食をしたと、『美津島町誌』に書いてある。かつては「お太子様参り」と言って、毎月15日・20日・28日の3回、お太子様にお参りをしたとも(『美津島町誌』)。
なお、隣村の久須保同様、大師堂の裏山は緒方独自の八十八カ所がある。

大師堂(月光山直観寺):お釈迦様の生誕日4月7日には、お年寄りが寺に集まりお釈迦様飾りをし、その後会食をしたという
姫神山砲台の最寄りの村だが
観光地として人気の姫神山砲台跡は、1902年(明治35年)、日本海海戦の3年前に建造された。着工は明治33年2月、翌年11月に竣工し、明治37年1月、日本海海戦の1年前に6門の28センチ榴弾砲が備え付けられた。
実戦では発砲することなくその役目を終えたが、石造りの兵舎、レンガ造りの弾薬庫などがレトロな雰囲気が醸し、対馬の新しい観光スポットとして人気を博している。
姫神山砲台跡に行くには、緒方の村のすぐ南を通るが、観光客がこの村に関心を示すことはない

緒方は人気の観光地「姫神山砲台跡」に最も近い村。砲台跡から緒方はこのように見える
【地名の由来】 「おかた」とは「小潟」のことで、その読みに字をあて「緒方」になったという説しか見当たらない。古い文書には「小潟浦」と記されているものもあるという
Ⓒ対馬全カタログ