2025年6月23日更新

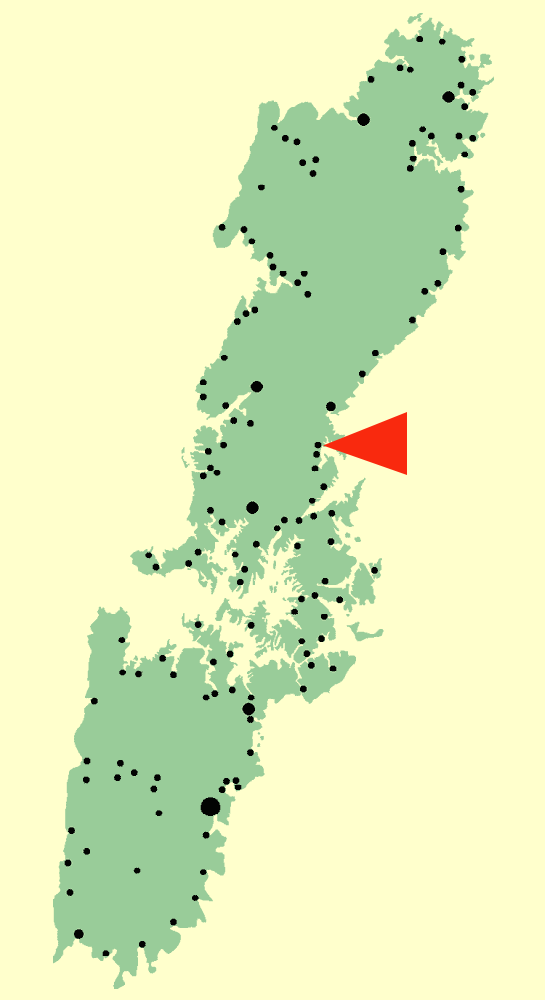
峰町
櫛
【くし】
弥生の誕生以来、侍はなく
村民自決の気風が
今につながる
小川をはさんで対峙する、櫛と位ノ端
一つの村だと思っていたら、全然違う村だった。初めて櫛を訪れた人は、誰だってそう思うに違いない。
例えば、かつての対馬には、豆酘瀬と佐須瀬とか、豆酘内院と与良内院とか、川をはさんで違う村というケースはあったが、川幅がそれなりに広いとか、納得できる理由があった。しかし、櫛の大地子川(ふちしのがわ)は、国土地理院の2万5千分の1地形図でも川を示す青い線すらないレベルの小さな川だった。
そもそもの原因は、江戸時代初期、1660年代半ばに行われた寛文の検地。税収の基となる土地の面積を求めるために村々の境界を定めなくてはならないが、曽村と櫛村の間では大地子川(ふちしのがわ)が境界となった。そして、それが三根郡と仁位郡の郡界でもあった。
その後、明治11年に対馬は上県郡と下県郡の二郡に分けられ、この小さな川が、二つの郡の境界、対馬を二分する大きな境界となった。架けられた橋の名も「郡界橋」となった。
対岸の曽側に家が建ち始めたのは明治の終わり頃。外来漁民が移住してからだった。小字名は、仁位(郡)の端だからと「位ノ端(いのはし)」と名付けられた。

櫛浦:橋の右側が峰町櫛。左側は豊玉町位ノ端

郡界橋:市の資料では架設年不明。現在は整備され、大地子川(ふちしのがわ)の川幅も広くなった。橋長5.8m、幅員3.3m(位ノ端側から撮影/2022年)
室町時代に村替え
かつて櫛村は一つ北の浦(おそらく現在のトクエ)にあったと言われている。おそらくそこで何百年も暮らしが営まれてきた。室町時代中頃、1437年(永享9年)、九州からやってきた修験者が現在の櫛浦の浦おくを開き、村人に村替えを促したという。
なぜ村替えを勧めたのか。その理由は記録にないが、当時の櫛村はとても狭かったのかも知れない。あるいは御託宣でもあったのだろうか。村人全員がそれに従ったかどうかもわからない。
村を拡張するのが目的だったのかも知れないが、新しい櫛が村の中心になり、現在に至っている。その修験者が他の村で似たような行動をとったという記録はないようだ。
かつては元の村を「古櫛(こぐし)」と呼んでいたそうだが、そのことを知っている人はほとんどいないという。

櫛周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大/字名・遺跡名追加等)、長崎県遺跡地図
古櫛は弥生の頃からの村か
この村の起こりを知るために、まず村替え前の櫛「古櫛」の地形を検討してみる。今でこそ埋め立てられているが、かつては大きな袋状の入江であり、周囲を小高い丘で囲まれていた。つまり風波をしのげ、船を係留するには最適な地形だった。
そして、付近の岬には弥生時代から古墳時代にかけての墳墓遺跡が点在している。
「松山遺跡」からは箱式石棺の材料となる板石が多数発見された。戦時中に畑にするために墳墓が破壊されたと考えられているが、数基の石棺が置かれていたと推測されている。弥生時代のものとされているが、その根拠はよくわからない。
古櫛から1kmほど沖の岬で発見された「エーガ崎遺跡」は当初は弥生時代の墳墓と言われたが、再発掘によって古墳時代の墳墓と修正されている。
松山遺跡がある丘の下で発見された「櫛のサエ遺跡」からはガラス製小玉多数、碧玉製管玉5、小形丸底壺、紡錘車などが出土。古墳時代の墳墓遺跡とされている。
また、対岸の岬で発見された「観音鼻遺跡は」、櫛関係の遺跡かどうかは明確ではないが、弥生時代後期の箱式石棺3基から長頸壺形土器、小形内行花分仿製鏡、銅釧(どうくしろ)などが出土している。
さらに、長崎県遺跡地図には掲載されていないが、南東に伸びる半島の先端部で発見されたのが「飯盛遺跡」。箱式石棺1基から鉄斧1個が出土し、弥生末から古墳時代前期のものと推定されている。
以上のことから、櫛には、弥生時代から古墳時代にかけて、村を統率する力をもった主(ぬし)がおり、交易を生業としていたかどうかはわからないが、交易船の停泊地、風待ちの港として利用され、朝鮮や九州と交流していたと想像できる。
なお、古櫛と思われるトクエは、大正元年測量の国土地理院2万5千分の1地形図では「突毛」と書き、「トッケ」とルビが打たれている。それが「トクエ」に変化したようだ。

櫛のサエ遺跡は、大きな建物(造船所)の裏側にあるが、現在は住宅のコンクリートの下になっている。

松山遺跡:櫛のさえ遺跡の上の丘の上にある弥生時代のものとされる墳墓遺跡。第二次世界大戦中に食糧増産のため畑地に。その折に多数の石棺が破壊された。現在は散乱していた石棺材を使って復元された箱式石棺が置かれている。 ※2023年時点では周囲の畑が防獣ネットで囲われている。遺跡に近づくことは困難
塩と魚の室町時代
村替えがあった頃、櫛では製塩が行われていたようだ。
1462年(寛正3年)、当時の島主より家臣に給付した宛行状に「くしのかま」という文言があり、当時の対馬の多くの村と同じように櫛にも塩竃があったことがわかる。
創業時期を伝える史料はないが、他の多くの塩竃が1300年代前半に始まっているところから、おそらく櫛も同様ではないかと思われる。
櫛はひたすら漁業や農業、製塩業と、生産する方に集中していた。村には侍は住まず、塩と魚で外の世界とつながり、必要なものを得ていた。
1471年に出された朝鮮の『海東諸国紀』 には戸数30戸と書かれているが、実際はその半分ほどではなかったか、あるいは塩竃関係の施設も含まれていたのでは、と言われている。

櫛浦から対馬海峡方面を撮影:一番手前の岬が観音崎
“侍がいない村”のデメリット、メリット
冒頭で述べたように、寛文の検地によって櫛集落のすぐ南を流れる大地子川(ふちしのがわ)が曽村との境界になってしまったが、これは給人(侍)のいる村といない村の力関係によるものではないだろうか。曽の中心から境界までは直線距離で1.8kmも離れている。
村の面積にしても曽が約328町歩もあるのに比べ、櫛は約90町歩。ちなみに北隣の佐賀は約221町歩、その北の志多賀は約222町歩だ。このあたりの村としては櫛だけが極端に狭い。そして櫛だけ給人がいなかった。(明治17年『上下県郡村誌』より)
農民は侍の決めたことに文句を言えなかった時代。村勢にも大きく影響したはずだ。もし室町時代の村替えがなければ、もっと狭くなっていたかも知れない。
侍がいないことは、身分や立場としての格差がない、あるいは少ないということにつながる。自分たちで村のことを考え、時には憂い、その行く末を心配し、それに対して解決策を探す。櫛の人々は昔からそのように生きてきたのではないだろうか。
余裕のない江戸時代の食糧事情
村域が狭いということは、おのずと耕作面積も狭くなる。明治になってのデータだが、櫛は12.7町歩、曽は27町歩だ。(明治17年『上下県郡村誌』より)
江戸時代の櫛の食糧事情を、物成(年貢)から計算し推測してみると、1700年(元禄13年)は一人当たり(10歳以上)年間の麦量(食糧)は0.63石、一人1日1.7合となる※。これは実は当時の対馬の平均よりも3割ほど多い。小さな浦の奥を畑に変えたり、木庭作に精を出したからだろう。
しかし、161年後の1861年(文久元年)は、一人当たり(11歳以上)年間の麦量(食糧)は0.34石、一人1日0.93合と、その頃の対馬の平均1.8合の約半分。麦の生産量の落ち込みは少ないが、人口が大きく30人増(10歳以下含まず)と、1.5倍に増えた結果だ。
孝行芋が加わり、さらに幕末期は村網が許されるなど、漁業禁止が緩和されていたので、漁業の方を頑張ったのだろうか。また、何かの事情(麦畑が塩水をかぶる等)で畑が使えなくなったか、管理がしやすい孝行芋の畑に変えたのかも知れない。
『峰町誌』に1884年(明治17年)のデータも載っているので、さらに23年後をみてみると、米は2.5石、麦は139.2石で、米麦合計で141.7石と、約20年で1.66倍。人口は1.3倍に増えたが、収獲量がそれを上回った。
1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』
物成約25石、戸数15、人口53、神社1、寺1、給人0、公役人10、肝煎1、猟師2、牛6、馬2、船1
1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』
籾麦85石、家21、人口100、男43、女40、10歳以下17、牛12、馬10、孝行芋1,500俵
1884年(明治17年)『上下県郡村誌』
米2.5石、麦139.2石、戸数29、人口129,牛28,馬16,船6、蕎麦52石、孝行芋15,000斤=9トン、干ワカメ6,000斤=3.6トン、スルメ500斤=300kg
※対馬藩の「物成(年貢)」は収穫量の1/4だが、それ以外に金銭で納める税金「公役銀」を工面するために麦などを売る必要があり、その他の支出も考慮すると、食糧として農民に残るのは収穫量の1/3くらいと考えられている。村によって多少事情が異なるのであくまでも計算値、目安と理解してほしい。
明治前期に始まっていた櫛のイカ漁
『峰町誌』に載っている1890年(明治23年)の『庶務統計』によると、櫛では28戸が漁業に携わっており、漁船は8艘あり、その内の1艘が鰯網船で、ほかの7艘はすべてイカ釣船。ほとんどの家が半農半漁だが、イカの漁期が秋から冬にかけてと農閑期であったため、イカ漁への進出はハードルが低かったのかも知れない。
対馬藩は島外漁師に漁を許しても、島民には採貝・採藻以外の漁業を長く禁止してきた。そんな櫛の人々がイカ漁と出会うには、イカ漁には欠かせないプロセスも功を奏したはずだ。
当時はイカはスルメにしなければ運べない。氷が手に入らず生のままでは商品にならなかったからだ。イカの加工業者は対馬に加工場を設置し、地元民を雇わなければいけない。おのずと島民とイカ漁との距離は縮まり、島民もイカ漁を覚える。
1884年(明治17年)の『上下県郡村誌』にも「スルメ500斤(300kg)」と記録されているように、島民の漁業就業が自由になった廃藩置県(明治5年)から12年後には、櫛の人たちは自らの手でスルメを生産、商品として出荷していた。
現在、櫛はイカ漁の村だが、そのベースは明治の初め頃にできていたということになる。

イカ釣り漁船が並ぶ雨の櫛漁港(2003年)
大櫛、小櫛、トクエ
現在の櫛は大きく3つの地区、「大櫛」「小櫛」「トクエ」に分けられる。さらに6地区に分けて、それぞれが一つの班として自治活動を行っているという。対馬では移住者及びその家系を「寄留」として区別してきたが、櫛では寄留の人たちは「浜組」と呼ばれ、「小櫛」に住み、金比羅神社を管理しているそうだ。
また、その本戸と寄留の区別も昭和50年代初め頃に取り払ったという。以前は本戸だけだった住吉神社の祭りにも、寄留の人たちが参加するようになっている。若者の流出、後継者不足で、双方とも地区の行事が守っていけない。そこで「一緒にやろう」ということになり、本戸・寄留の区別も、またそれを意識することもなくなってきているという。

大櫛:橋(郡界橋)から左側は豊玉町位ノ端

小櫛:外来漁民、いわゆる“寄留”が多く住む

トクエ:最初の櫛「古櫛」と推定。櫛の浮桟橋はトクエ側にある

櫛の住吉神社
【地名の由来】 クシは朝鮮語で岬をあらわす「串(こす)」に由来し、櫛周辺は岬の多い地形だからという。和歌山県の串本も同様の由来と言われている。また、周囲の地形、入江の入り込んだ形が櫛の形に似ているからという説もある。
Ⓒ対馬全カタログ