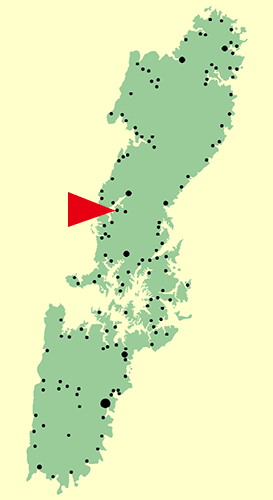2023年1月6日更新

峰町
賀佐
【かさ】
世帯数7、人口16人の
超過疎の村は、
ゴボウの村でもあった
最も過疎が進んだ村の一つ
この村が登場する最も古い文書が、1406年(応永13年)のものであり、鎌倉時代か室町初期には誕生していた思われる。
江戸時代中期(1700年)には21戸の家があり110人が住んでいた。末期の文久元年(1861年) も20戸に99人だ。最も人口が多かったのが1913年(大正2年)の135人だったが、その11年後(大正13年)には86人と、49名も減少。韓国併合後、さらに第一次世界大戦後の好景気もあり、本土や大陸に渡った人たちも多かったと思うが、賀佐ほど人口減少が目立った村は少なかったようだ。
第二次大戦後のベビーブームを経て、1955年(昭和30年)に92人まで増えるが、子供たちが育ち、高度経済成長期に入ると集団就職が始り、人口は減少の一途をたどった。平成に入ってからは、5~8戸、13~18人を推移。人口減少の激しい対馬の村の中でも“激甚”といっていい程の減りようだ。
平地の狭さは生産力=経済力の小ささに直結し、豊かさを求めると外に向かうしかない。しかもトンネル開通以前は陸の孤島。ここから厳原や鶏知へ通勤するのは不可能だ。
待望のトンネルができたのが2000年。超過疎が決定的になって10年以上。もっと早くトンネルができていれば少しは状況が変わっていたかも知れないが、土地の狭さは決定的だ。

小さな村だが、右奥に田畑が広がっている
かつては鯨漁に参加した時代もあった
浜(船着き場前)には恵美須神社が祀られている。かつての天道地に恵比寿の祠が設けられたものと考えられているが、恵比寿といえば漁業の神様だ。かつては漁業も盛んだったということだろう。江戸時代は藩によって島民の漁業が禁止され農業中心の暮らしとなったが、佐野網の請浦として漁に協力し、泉佐野の漁師が仕掛けた鰯網を引いたこともあったはずだ。
1678年(延宝6年)1月に、三根湾に2頭の鯨が迷い込んだので、狩尾と口江(狩尾の枝村)の2村が協力して突き取ったという記事が『毎日記』に載っている。その時、すぐに賀佐に声が掛かったかどうかは明記されていないが、賀佐は漁に間に合わず、分配には預かれなかった。
そのことを賀佐の下知人(役人)が届けると、今後は賀佐とも協力して漁をするようにというお達しがあったという。
1700年(元禄13年)3月に三根湾に迷い込んだセミクジラを賀佐、狩尾両村の網で立てきり、廻村の鯨組に突き取らせたという記録がある。あの一件以降、三根湾での鯨漁には賀佐も加われたということだろう。
明治時代も農業中心の村
明治17年に編纂された『上下県郡村誌』掲載の「峰村の物産調べ(表)」によると、峰村で海産物を産しないのは、三根、吉田、そして賀佐の3村だけだ。田畑の多い三根と吉田は納得できるが、賀佐のような湾の入口に近く平地の少ない村は、明治に入って藩の漁業禁止の規制がなくなると、半農半漁に戻るところが多かった。
しかし、賀佐には交通手段、運搬手段として欠かせない舟は3隻あったが、漁業従事者はいなかった。自家消費するだけの細々とした地先漁だったということだろう。
農産物といっても米はなく、大麦・小麦・が、大豆・蕎麦・粟・サツマイモ・苧(からむし:麻の一種)と、パッとしない。昔風に言うと「銀稼ぎ」ができない。これが過疎の理由の一番ではないだろうか。
※明治23年のデータでは漁船が1隻ある

賀佐のシンボルツリー、一本杉
「地名の由来」混迷の里
賀佐の地名の由来を過去の書籍に求めても、まったく説得力のあるものはない。三方の山が急峻で、民家を圧しているので、「嵩高し」「嵩にかかる」ところから、とか。伝説とか歴史的な事柄に由来するのであればいろいろ考えを巡らさなければならないが、地形が由来の場合は、もっとシンプルなのではないだろうか。
自分ごとで恐縮だご、取材で撮影したゴボウ畑の写真を後日見て、はたと気付き、閃いた。谷の奥の山が笠の形だ。「賀佐」の由来は、この山の形ではないだろうか。
“狭い浦の奥に鎮座する笠形の山”を2万5千分の1地形図で探すと、集落としては美津島町緒方くらいしかなく。どこにでもある景色ではない。
また、『峰町誌』には、地名の由来を考察する過程で、上県町の無人の浦「笠ヶ浦」の地名の由来を、その奥に笠山、笠の形をした山があるからとしながら、「賀佐」の由来としては昔からの説「嵩にかかる」を選んでいる。
真偽のほどはわからないが、昔々、狭い谷の奥にそびえる笠形の山を眺めて、美しい笠の形をした山だと感じ、ここを「かさ」と命名した。そのような気がしてならない。

谷の奥に見える山の形(笠形)が地名の由来か
多田氏の村として有名
1469年(応仁3年)に当時の島主・宗貞国より、賀佐に所領をもつ多田八郎左衛門にあてた宛行状(あてがいじょう)に、親類子供の居屋敷を給分としてとしてあてがわれたことが記されている。ことの詳細はわからないが、多田氏が室町時代中期から賀佐を領地とした給人であったことがわかる。
これが賀佐の多田氏の歴史初登場であるが、1703年(元禄16年)の『対州郷村帳抜書』には、賀佐には給人が住んでおらず、この頃はすでに給人多田氏は、府中城下に住む府内士(府士ともいう)になっていたということだろう。元禄の賀佐は農家(公役人)16軒、家数21の村だったようだ。(但し、当時も給人はいないが足軽はいたようだ。)
賀佐はとにかく多田姓の多いことで知られている。江戸時代初期に本家は府中に出て行ったが、分家、傍流の多田氏が公役人として多く賀佐に残り、断絶する家はあったものの、ほとんどそのまま現在に至ったということだろう。
吉田の開きまで手を出した賀佐人
時代は下るが、 天保期(1830年~1844年)の在郷給人の知行高をまとめた『八郷給人分限帳』によると、賀佐では給人2名(多田与市、多田繁蔵)が足軽から立身し、知行を得ている。
また、『吉田村落誌』は、1816年(文化13年)には、賀佐の足軽利吉が吉田の土地の開きを許された記録を紹介。さらに1817年(文化14年)に賀佐の給人多田与市が、吉田の開きを許され、その内の7分の3を賀佐の足軽惣左衛門に譲り渡したという記録を紹介している。幕末期には、賀佐には給人2名と足軽2名がいることになる。
賀佐の給人が吉田の開きに積極的に関わろうとするのは、その頃の賀佐は干拓できる湿地や干潟がほとんどなかったからだろう。そして、その頃の対馬藩で出世するには、開田で収入を増やし、藩に上納するのが最も確実な方法でもあった。
江戸時代から伝統産品、賀佐ゴボウ
前述の「峰村の物産調べ(表)」の項目にはないが、 1925年(大正14年)の 『峰村是』の農業生産総額のデータの中に、峰村としてだが「牛蒡(ごぼう)」という字が登場する。生産額は載っていないが、おそらく賀佐ではないだろうか。
昭和後期に発行された定期刊行物『対馬風土記』の第5号に、「多田のしゃくなに、賀佐ゴボウ」というフレーズが登場する。初物献上の定番であったと述べられているが、多田という村が存在した時代から考証すると、「賀佐ゴボウ」は江戸時代初期からあったと推測できる。
「賀佐と言えば、賀佐ゴボウ」。よく耳にするこのフレーズも、300年以上の歴史を誇るということかも知れない。
賀佐ゴボウの復活、そして持続へ
ゴボウは地中深く縦に伸びる。だから収穫するときは深く掘らなければならない。他の作物と違ってたいへんな重労働を強いる。だからこそ他の村ではあまり栽培されなかったが、賀佐は生きるためにゴボウを選び、成功した。だから、賀佐の人間は辛抱強い。
そう語るのは、100年以上の伝統を誇る「賀佐ゴボウ」を復活させ、次代に残そうと頑張っている日高安実氏。昭和の中頃からは各家で細々と栽培されるに留まってきたゴボウだったが、小型油圧ショベルを導入することによって生産軌道に乗せ、大々的にゴボウ農家としてデビューした。現在は、他家の休耕地も耕し、ゴボウだけでなく、ニンニク、牧草栽培にも取り組んでいる。今、賀佐には休耕地がない。

ゴボウ掘り出し光景
【地名の由来】本文参照
Ⓒ対馬全カタログ