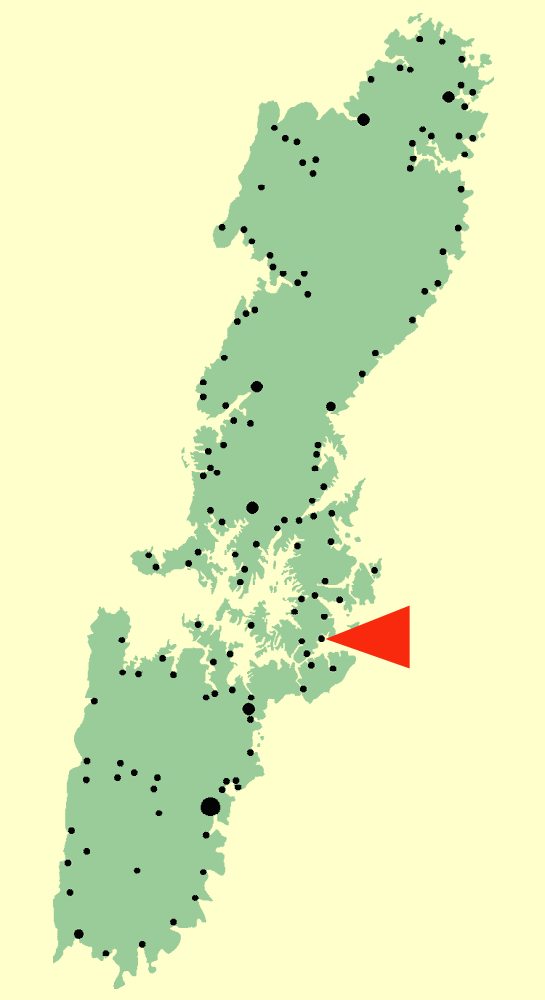2023年1月4日更新

美津島町
犬吠
【いぬぼえ】
名山「浅茅山」を背に
小さき村はいかに発展したか
・・平成年間は戸数減なし
地名の起源はやはり「犬」だろうか
空撮写真でわかるように、海側から見ると浦奥の先にどーんと浅茅山(あさじやま)が控えている。あの『万葉集』にも載っている、古からの名山だ。古人も思ったのではないだろうか。なんと美しい浦ではないか、と。
ただし、「犬吠」の文字が歴史に初めて登場するは、1700年(元禄13年)の『郷村帳』だ。そこには、戸数7戸、人口26人とある。最も小さい村の一つだ。(特殊事情の豊崎郷・津和原2戸を除く)
1809年(文化6年)に発刊された『津島紀事』に、「ある説にいう。この里は東目のかすかなる所にして山の上および船路よりも見えず。たまたま犬の吠ゆる声を聞きて人家の在る事を知り尋ね行きて見るに里の名もなきゆえ犬吠と名づく」とある。その地名の起源をやはり「犬」に求めているが、どうだろう。
※かつての「浅茅山」は、現在「大山岳」と呼ばれている。
浦名が先か、村名が先か
通常、村の名前と浦の名前は一致することが多いが、ここは違う。国土地理院の地形図によると、浦名は「黒崎浦」で「犬吠浦」ではない。村名があれば、やはり素直に考えれば浦名には村名を使うのではないだろうか。浦名が先にあり、その後に村が生まれたので、村名と浦名が違うようになったのでは。それが黒崎ではなく犬吠となったのにはそれなりの理由が、誰もが納得する理由があったからではないだろうか。
本当なのか冗談なのか、「犬吠では犬を飼わない。飼うと人に吠えかかり必ず咬みつくようになると、部落の人が言っているらしい」と1978年(昭和53年)発行の『美津島町誌』に書いてある。

浦奥から見た黒崎浦
かつては玉調とセットの村か
北隣の入道浦には弥生時代の遺跡があるが、犬吠のある黒崎浦では見つかっておらず、村の痕跡はない。また、室町時代の対馬の村の戸数を記した韓国の書『海東諸国紀』(1471年)に「犬吠」の名はない。付近の村(鴨居瀬・小船越・久須保・緒方)は載っているところから、中世に存在していたとしても、数軒だけの小さな村だったことが推察される。
『美津島町誌』には、1860年(安政7年)に著わされた『楽郊紀聞』に、犬吠の畑の地中から日本のものとは思われない(古代の中国か朝鮮のものと思われる)磁器らしき焼き物が発見されたと書いてある、とある。このことから町誌の著者は、「犬吠ー玉調ルート」という地峡を越える交易ルートが古代にあったのではないかと述べている。

犬吠も玉調も中世中期は埋立てもなく、海が浦の奥まで深く湾入していた。それを推測し地図に反映(透過部)。地形を考慮しつつ犬吠・玉調ルートを最短距離で考えてみた(最高地点で43m)
出典:国土地理院地形図(村名拡大、ルート記入等)
栄華盛衰も玉調とリンク?
中世の玉調は、犬吠の浦奥から山を越えて500mほどの浅茅湾側にあった。平安時代中期に編纂された『倭名類聚鈔』に、対馬の郷名として「玉調郷」が載っており、当時その郷の中心として玉調が栄えていたであろうことを考慮すれば、「犬吠ー玉調ルート」があったことは容易に想像できる。(その頃の村の名は犬吠ではなく、黒崎だったのかも知れない)
その郷の中心だったほどの玉調の村が、前述の『海東諸国紀』に載っていないということは、村勢が急激に衰えたということであり、それとリンクして犬吠も衰えたと解釈できないだろうか。大きな要因の一つは、小船越が倭寇の拠点の一つとして栄え、倭寇沈静後は朝鮮への渡航許可証である「文引」発行地として栄えたことで、「犬吠ー玉調ルート」が交易ルートとして利用されることがなくなったということではないだろうか。(文引発行は1430年頃から:「小船越」参照)
江戸時代に、7戸から14戸に
江戸時代元禄の頃(1700年前後)は、戸数7戸、人口30人くらいで、在郷給人や足軽という武士のいない村だった。その後、1772年(明和9年)の資料でも戸数は6~7戸と変化なく、約90年後の1861年(文久元年)の資料では、戸数14戸、人口55人と、ほぼ倍になっている。開き(干拓)によって畑が増えたからだろう。村全体で牛5頭、馬6頭を使う耕地を持っていた。
また、江戸時代、対馬では原則的に各村の漁業は禁止されていたが、後期になると村網(地曳網)が解禁され、イワシやキビナの小魚を獲り、イリコや干鰯(肥料)に加工して商品とした。犬吠の幕末期のイリコ生産請負量は100斤=60kgで、それほど多くはないが、戸数対比で他の村と比べると、対馬としては平均的な量だった。
1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』
物成約12石、戸数7、人口26、神社1、寺1、給人0、公役人4、肝煎1、猟師0、牛2、馬0、船2
1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』
籾麦99石、家14、人口55、男25、女27、10歳以下3、牛5、馬6、孝行芋560俵
過疎を感じない村のひとつ
明治になると、対馬では藩政時代のさまざまな規制が取り除かれ、農民でしかなかった島の人々も漁業が可能になった。また、旅漁師として対馬に出漁していた瀬戸内の漁師たちが、対馬に居を構えることができるようになり、人口も急速に増えた。明治時代の資料は見当たらないが、犬吠も1927年(大正13年)には戸数22戸、人口108人となっている。
2015年(平成27年)は、戸数54戸、人口164人。25年前と比べると、人口は約3割減っているが戸数はまったく変わらない。少子高齢化が主な原因だろうが、戸数が変わらないのは、対馬の村としては素晴らしい。対馬としてはあまり過疎を感じない村の一つといえる。

恵比須神社は山の上から村を見守る
【地名の由来】由来不明。本文で紹介している説の他に、『美津島町誌』では、イヌの「小さい,狭い,低い」などにそっくりあてはまるのではないか。「狭い小さな部落」という意味ではないか、と解釈しているが、「イヌ」の意味の根拠がわからず、理解困難。
Ⓒ対馬全カタログ