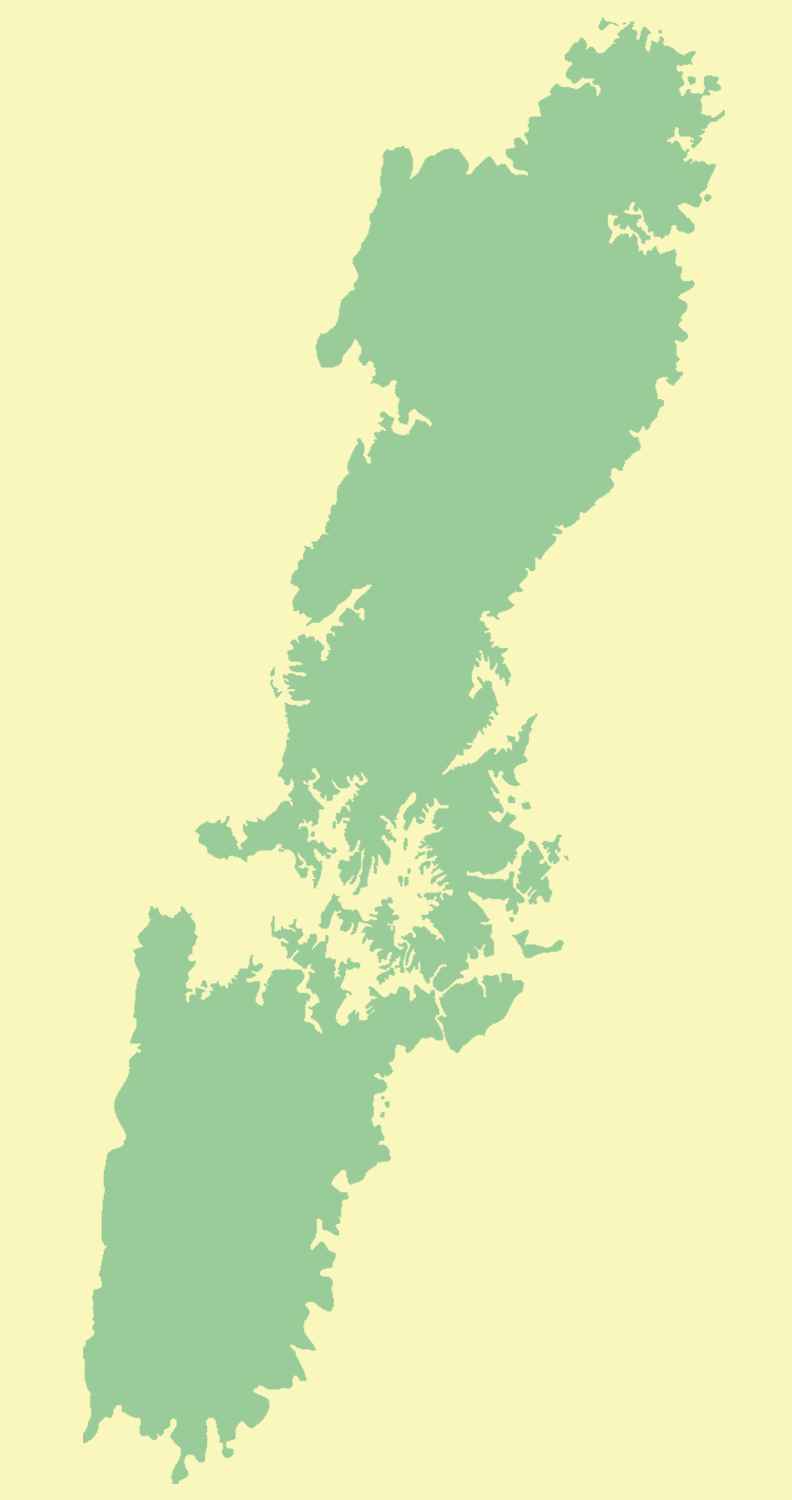2022年2月6日更新

対馬焼
【つしまやき】
朝鮮焼で培った感性と技術。
江戸初期からつながる
対馬ならではの美の系譜
対馬焼とは、対馬人による朝鮮陶
「対馬焼とは?」という問いをネットで検索すると、おおむね次のような文言に収まる。
「対馬から産出した焼き物。一般には朝鮮釜山窯のものも含めていう。対馬では享保年間(1716~1736年)に朝鮮の陶法が伝えられ始まった。」
江戸時代の対馬では、朝鮮で焼かれた焼き物は「朝鮮焼」と呼ばれ、“朝鮮焼の技術は藩の秘伝”といわれた。その秘伝の継承に藩は支援を行い、ある時は藩自らが窯を経営した。

釜山窯で焼かれた朝鮮焼の茶碗 綴じ目秋草文 写真:國分英俊氏
「わび」「さび」を具現した対馬焼
安土桃山時代に大名たちに“茶”が広がると、「わび」「さび」という、茶道の精神と響き合う器として「高麗茶碗」が求められるようになり、そこに対馬藩は商機を見い出した。(時代はすでに「李氏朝鮮」だが、茶碗は「高麗茶碗」と呼ばれた。)
釜山の出先機関「倭館」に窯(釜山窯)をつくり、そこで大名や豪商たちのニーズに応える高麗茶碗を焼かせた。これが対馬焼の原点だ。(「商機」といっても、実は“藩の存在価値”を高め、人脈を形成・維持するのが主目的で、対馬を潤おす“商い”ではなかったが。)
ただ前述のネットの説明には明らかな間違いがある、対馬で対馬焼が始まったのは享保年間(1716~36年)ではなく、明暦年間(1655-58年)。一般に知られているより60~70年も前から始まっていた。
(以下の対馬焼に関する説明は、対馬藩の文書記録を徹底精査し、過去の通説を覆した泉澄一著『近世対馬陶窯史の研究』(1991年)を基にしている。)
実は幅広い対馬焼の製法&意匠
対馬焼は、朝鮮焼を手本としている。これが対馬焼の最大の特徴ともいえるだろう。製法の違いなどによって、井戸、三島、粉引、刷毛目、御所丸、雲鶴、立鶴、半使(ハンス)、伊羅保など、さまざまな呼び名があるように、デザインバリエーションは多い。
「立鶴(たちづる)」は志賀窯(江戸時代中期~後期の対馬焼の窯)オリジナルと、かつて言われたこともあるが、これは3代将軍の徳川家光が大名茶人であった細川忠興の喜寿の祝いの席で描いた絵が元になっているといわれており、それを茶の巨人・小堀遠州が発注用のデザイン画(「御本」という)を仕上げ、対馬藩経由で朝鮮でつくらせたもの。「立鶴」はその後、対馬焼の代表的デザインの一つとなった。

昭和後期に対馬焼を追求した対州窯 玖須朋弘氏の「御本立鶴茶碗」
対馬焼の源流は、朝鮮焼
江戸時代初期、安土桃山時代から続く大名たちの茶の湯好みと朝鮮陶磁器需要に応えようと、対馬藩では日本人好みの高麗ものを、本場の釜山の倭館で作らせた。その作陶の監督「茶碗焼役」あるいは「燔師」として藩は藩士を送り込み、大名たちが発注した御手本通りの茶碗(それを「御本茶碗(ごほんちゃわん)」という)などを作らせたが、やはりそれぞれのセンスや指導能力によって作品の出来に差があった。
上手と名高いのが、茂三・玄悦・小道二・小道三・弥平太・太平・徳本の7人。現代でも名前が知られているのが、伝世品が残されている中庭茂三、 船橋玄悦、松村弥平太だ。彼らが対馬焼の源流をつくったと言えるだろう。対馬藩の記録文書では釜山窯でつくったものを「朝鮮焼」と呼んでいる。
朝鮮焼ではない対馬焼をめざして
そもそも対馬の土器製造の歴史は古く、出土破片からみると新羅・百済の時代まで遡るそうだ。中世と言われる時代も、作陶はされていた。しかし確かな史料があるのは、江戸時代の明暦年間(1655-58)以後で、対馬藩が朝鮮の陶工を使って「高麗もの」と呼ばれた李朝陶器を作らせた釜山窯(倭館窯とも)全盛の頃からだ。
当初は釜山窯と同様の「朝鮮焼」を作陶しており、1660年(万治3年)の史料に「対馬焼の茶碗(似高麗茶碗)」という記述がある。以酊庵任務を終えた僧から土産に贈られた茶碗のことを、当時茶人として、目利きとして高名な京都・相国寺の鳳林和尚が書き留めた一文だが、対馬焼の技術の高さがうかがえる。
しかし、それが藩独占の「朝鮮焼」の価値を下げることにつながるとして、約100年間にわたり「朝鮮焼似」の焼物は禁止になった。あくまでも藩中心の沙汰だが、作陶のベースとなる対馬の土は、朝鮮の土とほぼ同質の土。さらに長きにわたり育まれた感性は朝鮮の作陶。自ずと「朝鮮焼」「高麗もの」の流れをくんだものになった。
時代とともに栄華盛衰した対馬焼
窯はいずれも府中(対馬市厳原町市街)近郊にあった。
小浦皿山窯は、記録にはないが、高麗青磁に近い破片が残されているところから、対馬諸窯の中で最も古いと考えられている。
久田窯は、窯のあった土地の名から増田窯とも称し、記録に残っているだけでも、明暦年間(1655~1658年)、天和年間(1681年から数年)、正徳ー享保年間(1714~1718?年)の3期があるが、それ以前からあったことが記録からうかがえる。
志賀窯は、対馬焼の中心をなすもので、大きく4期に分けられる。最初の志賀窯は釜山窯で陶工として働いた二人で開窯され、享保・元文年間の10年あまり(1725~1736?年)営まれた。商いとして成立させるために商人と手を組み、一時は上方まで販路を拡大した。
第2期は、いつの間にか始まっていた。寛延4年(1751年)に商人丸嶋屋利助から出された開窯願を受理し許可したものの、藩はその後の事業を把握しておらず、運上銀滞納にも気付かず、さらに「朝鮮焼似」の茶碗の出荷も見逃してしまうという失態を演じた。 1762年(宝暦12年)に気付いた藩が運上銀納入を命じると、窯出し完了後にそそくさと閉窯したようだ。
なんともちゃっかりした経営者だが、この第2期が、その後の志賀窯の運命を大きく変えることになった。

2021年の志賀:写真中央部のどこかに窯があったようだ
藩の政策変更で、藩窯プロジェクト始動
第2期で陶工として雇われたのは、釜山で作陶の修行を積んできた早田貞平だった。貞平はおよそ11年間、藩のミスのおかげで検分を免れ、朝鮮で学んだ技術を存分にいかして「朝鮮焼似」の焼物を作り続けた。そして、その技術は子の早田忠助に、孫の早田恵作に受け継がれ、志賀窯の伝統をつくることになった。
また、藩窯から民窯にかわった釜山窯は、1743年(寛保3年)、朝鮮での材料調達が難しくなり、さらに藩財政の逼迫もあり、ついに閉鎖。藩庫の朝鮮焼の在庫が少なくなると、藩は方針を転換。今度は「朝鮮焼風」の焼物を製陶させるため、さらに島内に流通している伊万里焼の輸入による銀流出を防ぐ目的で「伊万里焼風」の日用品をつくるために、藩窯として志賀窯の再興に取り組んだ。その後20数年間、人を変え何度もチャレンジしたが、やっと4度目で成功にこぎ着けた。
藩の期待に応えた早田親子の志賀窯
そのプロジェクトを成功させたのは、早田貞平の子・忠助と孫の恵作だった。藩の依頼で着手した1791年(寛政3年)、忠助は80歳、恵作は58歳で、忠助は翌年に亡くなり、恵作が窯を取り仕切った。
盛期としては第3期ともいえる志賀窯は、寛政・享和年間(1791~1801)、新渡茶碗(しんとちゃわん:当時の“現代”朝鮮焼茶碗)を主に生産した。藩の目的は朝鮮焼の技術を中絶させないことと、藩の朝鮮焼の在庫充実の2点に絞られた。早田恵作は藩の期待に応え、朝鮮からの輸入品と差のないレベルの作品をつくり、藩の御用品もすべて恵作作となったが、十分な備蓄量に達したことと、さらに藩への納入金問題があったのか、突然藩から廃窯の達しがあり、1801年(享和元年)あえなく閉窯となった。
その後、1804年(文化元年)に、70歳の恵作を担ぎ上げ志賀窯再興が図られたが、経営がうまくいかず9年ほどでフェードアウト。それと重なるように、まったくの新参者が藩に開窯を願い出た。
異色の陶工「又市」の本職は船頭
その志賀窯第4期ともいえる盛期を担った吉田又市の職業は、船頭だった。船頭といっても藩士で、船頭としての仕事は年に1回だが、藩の務めで長期の航海に出ることもあった。そんな彼がどうして焼物をしたいと思ったのか不思議だが、藩にとっては渡りに船、その願いは聞き届けられた。
そして、朝鮮焼作陶の指導役として79歳になった早田恵作を“みかじめ役”として任命。又市は船頭をしながらの修行で、一人前になるのに2年を要した。
1813年(文化10年)に開窯した吉田又市は、1816年(文化13年)、恵作引退後に志賀窯の“みかじめ役”に任命された。しかし、又市の窯「志賀茶碗窯」は“御用窯”ではあったが、藩窯ではなく、経営者はあくまでも又市だった。
“みかじめ役”の実態は不明だが、技術伝承者的な意味合いが強く、現在の日本では“伝統工芸技能者”、ドイツでいえば“マイスター”というところではないだろうか。自らも作陶し、弟子たちに技術を教えていたと考えられている。
1832年(天保3年)、又市は窯を自宅のある田渕に移したいと藩に申し出て、それが認められている。理由は、志賀窯で製品の紛失が多発しているので、より管理を徹底させるため。場所は特定できないらしいが、田渕にあっても窯の名前は「志賀茶碗窯」のままだった。

年代は特定できないが江戸時代に焼かれた志賀焼 雲鶴茶碗 写真:國分英俊氏
藩の積年の目標を達成した、志賀茶碗窯
藩が志賀焼を支援する目的の一つに、島内で使われる陶磁器をすべて島内産で賄い、島外への銀の流出を防ぐという大義名分があった。そして、ついに1827年(文政10年)、国内(島内)はすべて志賀焼を用いるように、という通達が発せられた。
又市の志賀焼は完成度も高く、伊万里焼に負けないと藩が太鼓判を押したようなもので、新たに藩庁内で使う焼物もすべて志賀焼になった。
吉田又市は1840年(天保11年)に66歳で亡くなったが、その前年まで船頭としても藩の御用を務めた。志賀茶碗窯は養子の保右衛門が継いだが、その後の志賀茶碗窯を伝える記録は、宗家文書からは発見されていない。
1859年(安政6年)の記録によると、その頃は阿須窯だけが操業していたことがうかがえ、おそらく嘉永年代末(1853~54年)には閉窯していたのではないかと推測されている。(『近世対馬陶窯史の研究』より)

志賀茶碗 鉄絵(年代不明)
志賀焼の流れを汲む小浦窯
吉田又市の弟子に棧原久右衛門がいた。その久右衛門の次男・愛助が1887年(明治20年)頃(史料で確認できるのは1897年頃)に小浦窯を開いた。志賀焼の伝統を継ぐことを第一義とし、窯出し後に商品となったのは出来のよい1割ほどで、当然価格も高くなり、対馬島内では流通しなかったようだ。
志は高かったが、経営が成り行かなくなり、1903~4年には廃窯になったと考えられている。
その後、棧原愛助の子・康人は、厳原の商人・茂村源助の出資、経営によって、志賀の地に開設された茂村窯業所を任されるが、方向性の違いで袂を分かつことになり、しばらくして退社。茂村窯業所も1920年頃には廃業したようだ。

明治から大正にかけて焼かれた志賀焼茶碗(右:茂村窯業所、左:不明) 写真:國分英俊氏
< 対馬の伊万里焼の歴史 >
倉田万兵衛による民間窯、立亀窯
下級藩士であった倉田万兵衛は1779年~1984年の5年間、藩から志賀窯の差配役を命じられ、藩窯として志賀窯を再興するプロジェクトを任されたことがあった。その後、部署が変わるとともに閉窯することになったが、おそらく作陶への思いは失われていなかったのではないだろうか。
立亀窯は、その万兵衛によって、1792年(寛政4年)に開窯されたとみられている。57歳で隠居して2年後、ちょうど早田忠助と恵作による志賀窯再興プロジェクト始動からやや遅れてのスタートだった。しかし、翌年、万兵衛は藍作りの指導で仁田地区に派遣され、窯場のことは職人の順蔵に任せ、自身は経営のみに携わった。
立亀窯は、厳原港の東岸にそびえる立亀岩の南側に設営され、今でも場所が特定できる数少ない窯だ。志賀窯と違い、朝鮮焼ではなく伊万里系の磁器を生産。まず島内に供給することをめざし、その後朝鮮への輸出にも力を入れた。そのためには優秀な陶工を得ることが最優先課題であり、立亀窯は優れた旅職人によって維持された。順蔵は旅職人をまとめる「竈立」職人として活躍し、初期の立亀窯製の焼物の底には、順蔵の一字を入れ「立亀順製」と銘記されているものがある。

立亀窯 福文字皿破片 写真:國分英俊氏

立亀窯は立亀岩の裏、この辺にあった(2003年撮影)
万兵衛孫の伝蔵と、印束小次郎の立亀窯
1806年(文化3年)に万兵衛が亡くなると、孫の伝蔵が跡を継いだ。立亀窯の宿命である職人の確保に苦労していたようで、宗家文庫にも、旅職人雇い入れの申し出書が多数残されている。
1816年(文化13年)に伝蔵が江戸詰めになると、義兄の印束小次郎が差配役となり、立亀窯を継いだ。1823年(文政6年)の宗家文書には、卯吉という対馬人の職人を「竈立」職人に格上げすることの申請があり、認められたことが記されている。なお、卯吉の一字を入れた「立亀卯製」が記された立亀焼はこの頃のものだ。
卯吉のおかげ等もあり生産は順調で、かつ印束小次郎の手腕によって立亀窯の経営は安定した。また、小次郎は朝鮮への輸出にも積極的であったらしく、立亀窯だけでなく田代領で作られた伊万里焼も独占的に商っていた。
そんな華々しい活躍を誇っていた小次郎だが、1841年(天保12年)、藩に持病の悪化を理由に隠退願いを出し、窯の経営から手を引くことになった。52歳だった。
その数年後、倉田伝蔵の子・弥三右衛門によって一時再興されるが、記録から推測すると嘉永年代末頃(1853~54年)に、阿須窯の開窯と入れ替わるように、60余年の歴史に幕を閉じたと考えられている。
初めから藩窯としてスタートした阿須窯
阿須窯は、厳原市街の北東、阿須湾に面した藩の阿須屋敷内にあった。職人の来島記録から、1855年か1856年に開窯したと推測されている。
明らかに藩が経営する、いわゆる藩窯だったが、焼成されたのは対馬焼ではなく、伊万里系の磁器だった。目的は、島内の需要を満たすことと、朝鮮への輸出だった。
しかし、開窯してから約6年後の1862年(文久2年)、わざわざ呼び寄せた職人たちを帰しているところから、この頃に閉窯したと考えられている。
Ⓒ対馬全カタログ