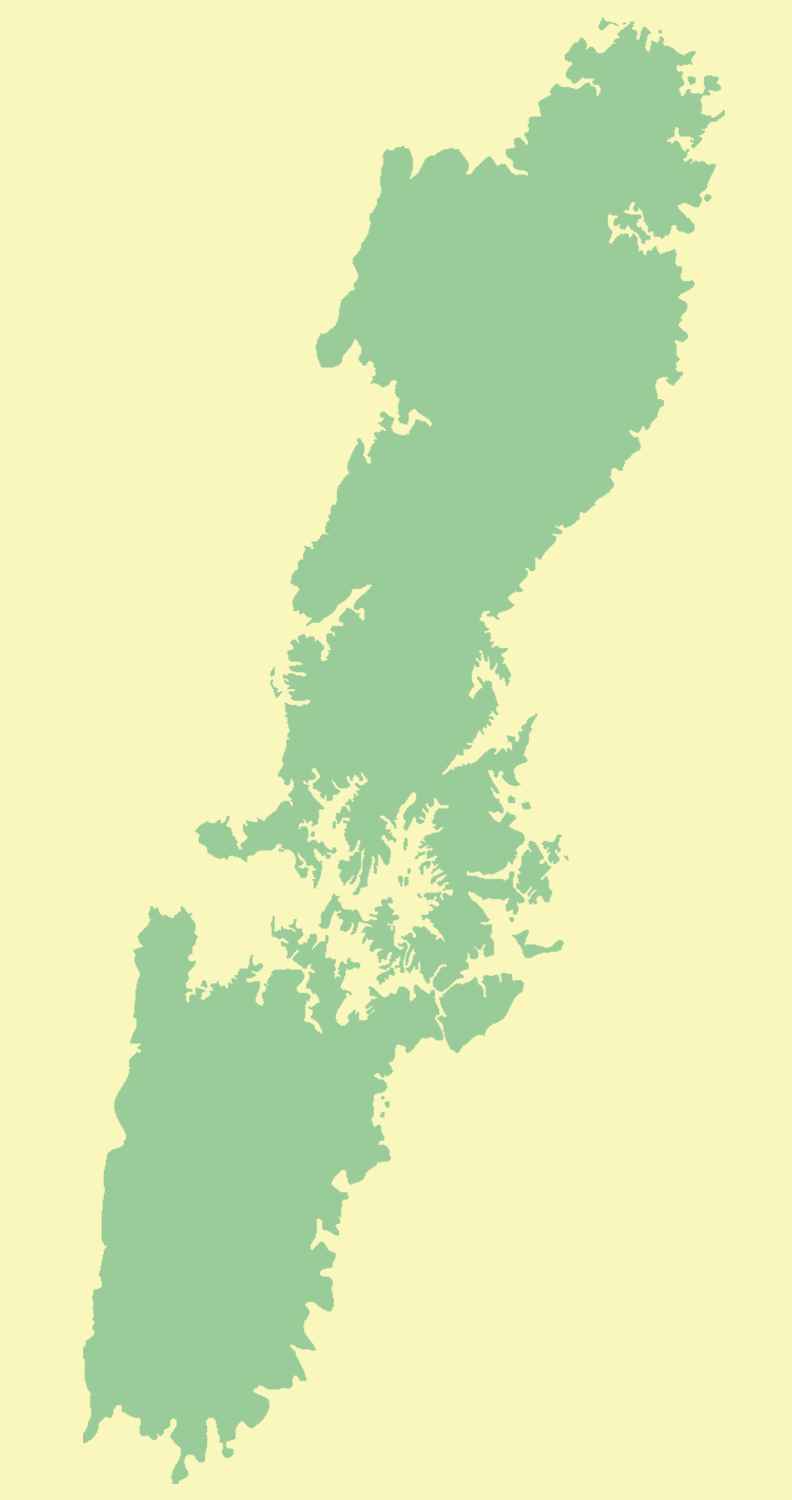2022年1月31日更新

写真:國分英俊氏
釜山窯
【ぷさんがま】
朝鮮の土、朝鮮人陶工の技、
対馬人陶工頭のセンスと能力、
そして、日本人の美意識
茶人好みの高麗茶碗をつくために
江戸時代初期、安土桃山時代から続く大名たちの茶の湯嗜好と朝鮮陶磁器需要に応えようと、対馬藩では日本人好みの“高麗もの”を、本場の釜山の倭館で作らせた。その作陶の指揮を執った陶工頭(今風に言えばディレクター)である「茶碗焼役」として、藩は藩士あるいは茶湯の指導者(茶道頭や茶坊主)を送り込み、大名たちが発注した御手本通りの茶碗(それを「御本茶碗(ごほんちゃわん)」という)などを作らせた。歴代茶碗焼役の総数、20数名。それぞれのセンスや指導能力によって、作品の出来や味わいに差があった。
上手と名高いのが、茂三・玄悦・道二・意三・弥平太の5人。その中で、現代でも茶陶の世界で広く名前が知られているのが、担当の期間が長く(それだけ優秀だったということか)、伝世品が多く残されている、中庭茂三、松村弥平太の2人だ。彼らを中心に、櫓漕ぎ船に揺られて朝鮮海峡を渡り、冬の釜山で作陶のディレクションに奮闘した茶碗焼役たちが、その後の対馬焼の源流をつくった。
(以下の釜山窯に関する説明は、対馬藩の文書や朝鮮側の記録を徹底精査して完成した泉澄一著『釜山窯の史的研究』(1986年)を基にしている。)
藩窯の釜山窯は約80年間
その始まりは、江戸の宗家屋敷を訪れた幕閣たち(酒井忠勝・柳生宗矩・金地院崇伝など)への茶碗進上だった。それが発展し、大名たちから注文を受けて朝鮮で焼かすという段階を経て、対馬藩は倭館内への陶窯設置を朝鮮側に要望した。倭館とは対馬藩の外交施設だが広大な敷地をあてがわれた。
1639年(寛永16年)に倭館外ではあったが窯を開き、その5年後の1644年(正保元年)に倭館内での開窯にこぎつけた。この時に活躍したのが、当時外交を担当した有田杢兵衛だった。それから1718年(享保3年)の藩窯・釜山窯の閉窯まで、倭館内、龍頭山の西側に陶窯が置かれた。
また、釜山窯は連続して運営されたわけではなく、開窯と閉窯を繰り返していたというのが実情だ。7年間火入れが行われなかったこともあるし、2年間連続して焼成されることもあった。
そして、開窯の度に問題になったのが、陶土の調達だった。対馬藩は、倭館を通して朝鮮側(東萊府)に開窯の予定を伝えると同時に陶土の供給要請「陶土求請」をするのだが、この交渉がスムーズにいくのは珍しかった。後半になるほど朝鮮廟道(びょうどう:朝廷)が頑なになり、何年も待たされることもあった。間に挟まれた訳官(通訳)が、自分が確保している陶土「内証土(ないしょど)」を提供してくれることもあった。但し、内緒土は高価だった。
1700年代に入ると、陶土だけでなく陶工の調達も難しくなり、ついに藩は1718年に閉窯を決意。藩としては釜山窯を終了するつもりはなかったようだが、結果的にこれが最後の閉窯となり、約80年の歴史に幕を引くことになった。
「朝鮮焼」には「判事茶碗」にないものがある
対馬藩の慶弔行事や祝事参列のため、朝鮮から「訳官」と呼ばれるバイリンガル外交官が派遣されたが、来島の際に朝鮮の茶碗を大量に持ち込み、それを対馬藩が買い上げることが常態化していた。それらの茶碗を「判事茶碗」といい、それは朝鮮で流通している茶碗で、朝鮮のセンスで作られていた。それを対馬藩は、家臣への褒美や大名への進物に使ったが、大名たちからの評判はイマイチだった。
当時の上流階級であった大名たちは、朝鮮の焼物に茶陶としての価値を見いだし、「高麗茶碗」は茶湯の世界で至高の器であったが、それは侘び・寂びという美意識が感じられればこそであった。やはり多くの判事茶碗にはそれが希薄だった。そして、対馬藩の茶道頭や茶坊主が陶工頭として指導し、釜山窯で焼いたものには、それがあった。これこそが対馬藩営釜山窯の存在意義だった。
対馬藩の記録文書では釜山窯でつくったものを「朝鮮焼」と呼び、判事茶碗ともども朝鮮焼物は「御茶湯蔵」と呼ばれる藩庫に保管された。

禅の悟りを表わす「円相」という日本の意匠と、朝鮮半島の土 。釜山窯産かどうかは不明
初期の釜山窯
1639年(寛永16年)に倭館外で始まった釜山窯は、外交官(役職名「裁判」)有田杢兵衛の外交手腕とねばり強い交渉等によって、その5年後に倭館内の開窯にこぎつけた。一度既定路線ができあがってしまうと、その後は官僚的・事務的な交渉で、陶土も陶工も薪木も比較的容易に得ることができ、対馬藩にとっていい時代だったと言える。
藩主は宗義成(1604~1657年)の時代。陶工頭としては、吉賀判太夫、渡辺伝次郎、古川林斎、船橋玄悦(1654年)、鳥井道喜(1655年)、中山意三(1655年、1656年)たちが活躍した。武家茶道も初期の勢いがあり、特にこの頃の対馬藩の記録に頻繁に登場した大名が、酒井讃岐守忠勝、柳生但馬守宗矩だ。
柳生宗矩といえば、あの柳生一族の当主であり、将軍家光の兵法指南役であり、当代きっての剣術家。禅にも通じていたとあるから、そこから茶道、茶陶へと広がったのだろう。最も厳しい政治家という一面をもつ柳生宗矩が対馬藩と懇意にし、そこから手に入れた朝鮮焼を愛でていたという事実は、朝鮮焼の魅力の一端を伝えてくれる。
また、将軍家や幕閣発注の御本茶碗の下絵を描いたのは、幕府の御用絵師だった狩野派の絵師たちと言われており、この時代であれば狩野探幽がその筆頭。各大名の下絵の絵師も高名な絵師だったことが想像できる。下絵の意匠のレベルの高さが高麗茶碗(朝鮮焼)の美をさらに高め、陶工頭たちの美意識を養い、朝鮮焼を育んだとも言えるのではないだろうか。
茂三が活躍した中期の釜山窯
中期は1657年に18歳で襲封した3代藩主宗義真(1639~1702年)の治世とほぼ重なる。朝鮮焼を珍重した大名も変わり、稲葉美濃守正則や、当時の藩主宗義真の姉婿である松平備前守正信の名が宗家文書に多く登場するようになった。武家茶道も盛期を迎え、注文も多様化し、より多くの陶工や絵師も必要になってきたようだ。
陶工頭としては、船橋玄悦(1663年)や、中庭茂三(1665年、1669年、1676年、1678年、1680年,1685年など、9回渡釜)、宮川道二、 長留藤左衛門がよく知られている。
初期と大きく違うのは、釜山窯の規模が大きくなったことだ。初期の陶工頭の赴任はほとんどが一人で、同行する細工師も数名だった。しかし義真時代になると、陶工頭5名が派遣されることも多く、1673年(寛文13年)の釜山窯は30人態勢となった。
釜山窯はどちらかといえば国のVIPへのサービス事業であり、財政を潤すための事業ではない。ある意味、藩財政の金喰い虫なのだ。良く言えば“目に見えない投資”だが、それも財政にゆとりがあればこそで、とにかく義真は色々な事業に手を出し過ぎた(※1)。おそらく義真は拡大志向、攻めの性格なのだろう。釜山窯の大規模化の要因の一つは、その義真の性格もあるではないだろうか。まだ好調だった日朝貿易がベースにあるとはいえ、やはり放漫経営という評価を受けざるを得ない。
1678年(延宝6年)には、対馬藩が長年要望してきた倭館の移転が実現した。その移転を認めさせた要因の一つが、釜山窯から出火した火事が倭館のすべてを焼失させたことだった。新倭館敷地には龍頭山(標高180m)を中心とした約10万坪、古館の約10倍の広大な土地が当てられた。館守屋敷や倉庫群は山の東側に、新釜山窯は龍頭山南西麓に建造され、費用の多くは朝鮮側が負担した。対馬藩の負担は、主要庁舎以外の建物、住居、倉庫、陶窯などだった。
※1 1659年(万治2年)、阿須川を開削。1659年(万治3年)、お船江を造成。1672年(寛文12年)、大船越瀬戸を開削。1678年(延宝6年)、桟原新屋形を建造。

延宝6年の草梁倭館竣工図(上が西) :窯は破線赤丸の辺りと推定される

窯場風景(釜山市観光案内板より)
弥平太の時代へ。後期の釜山窯
元禄時代(1688~1704年)以後の釜山窯の最大の特徴は、開窯期間が短期で断続的ではなく、長期間連続して開かれていたことだ。元禄になると、4回の訳官来島があったものの、判事茶碗を買い入れた記録がなく、そのための在庫不足を補うため、製造に力を入れたのではないかと推測されている。
また、後期に入ると、茂三から宮川道二を経て、松村弥平太に世代交代が行われ、後期のほとんどは弥平太が作陶を取り仕切ることになった。活躍した陶工頭も、宮川道二(1685年、1687年6月~1690年5月の約3年間釜山に滞在)と、松村弥平太の2名。弥平太は釜山窯に関わった期間が23年と長く、釜山滞在日数が最も多い陶工頭となった。
また、朝鮮焼の人気は弥平太の焼成で維持することができ、 阿部豊後守正武、土屋相模守政直など新たなファンを得ることができたが、義真時代の放漫経営のツケがまわって藩財政は逼迫。陶工頭をはじめ陶工たちへの給金も、茂三の頃に比べると半分となった。
さらに、元禄時代後期からは朝鮮側からの陶土供給が滞るようになり、1713年(正徳3年)~1718年(享保3年)の開窯を最後に、藩窯の釜山窯は開かれなくなった。最後の窯の陶工頭は、23年ぶりの釜山窯勤務となる宮川道二と、その後を引き継いだ平山意春だった。
※松村弥平太の陶工頭就任期間:1688年5月~1689年5月、1690年4月~1694年12月、1695年6月~1697年4月、1698年7月~1700年8月、1701年10月~1708年6月(閉窯直前に死亡)。(1676~1677年には陶工として赴任)
藩窯終了後、半官半民の釜山窯が誕生
その20年後、1738年(元文3年)、藩窯としてではなく、町民(小寺小十郎と早田貞平)が運営する民窯として釜山窯が再開された。民窯に藩が発注するという形で、朝鮮での調達が難しい陶土は、対馬から運んだり、倭館沖の牧の島(現 絶影島)の土で間に合わせた。焼かれたものが「小十郎焼」と記録されているところから、小十郎が陶工頭兼陶工で、早田貞平は一陶工というところだろうか。30人が従事したこともある藩窯時代とは違い、4人だけの小規模な製陶所だった。
1743年(寛保3年)になると、釜山での材料調達がさらに難しくなり、藩財政の逼迫もあり、対馬藩はついに半官半民の釜山窯も閉鎖。帰島して後の小寺小十郎の記録はないが、早田貞平はその後、対馬焼(志賀焼)の基礎をつくることになった。
陶工頭の仕事
倭館釜山窯は朝鮮では「倭館燔造所(はんぞうしょ=製陶場)」とよばれ、陶工頭は「燔師」と呼ばれた。陶工頭にとって重要な仕事とは、陶土の調合、細工人への作陶上の指示、窯の火入れ・温度の調整、といわれる。
陶工頭は「差倭」であった。「差倭」とは、朝鮮政府が公式の使者として認めた日本人のことで、「差倭」には朝鮮側から食料等が供給された。陶工頭は、陶器製造を求める使者ということで「差倭」として扱われたが、その長期滞在は朝鮮にとっては大きな負担でもあった。だから陶土の供給が遅れることによって、陶工頭の釜山滞在が長引くことは、朝鮮側への圧力としての効果もあったのだった。
また、陶工頭を務めた茶湯頭たちは、釜山に赴任するだけでなく、江戸や京都に出向き、営業のようなことをすることもあった。茶道の第一人者や大名たちを訪ね、どのような茶碗を欲しているのか直接リサーチするのだ。
<陶工頭一覧>
宗家文書に残る陶工頭たちの名と、わかる範囲でその渡航年を記しておきたい。
・吉賀判太夫 1639年 1645年
・蔵田弥三右衛門 1639年 1645年
・橋倉(端倉)忠助 1644年
・渡辺伝次郎 1642年 1647年
・鳥井道喜 1655年
・古川(大浦)林斎
・船橋玄悦
・宮川道庵
・鳥井道喜
・中山意三
・小田喜左衛門
・青柳善右衛門
・中庭(阿比留)茂三 1665年、1666年、1669年、1670年、1673年、1676年、1678年、1681年、1685年と、20年間に9回も陶工頭を務めた。1694年8月18日没。長寿院に墓がある。
・波多野重右衛門
・宮川道二 宮川道庵の子
・長留市左衛門
・長留藤左衛門 長留市左衛門の子
・長留三郎左衛門
・国部知斎
・藤川茂兵衛
・松村弥平太 1676~77年、1688~1708年、計23年も陶工頭を務め、1690年以後は道二に代り陶工頭トップとして活躍。持病があり対馬に帰る直前に釜山で死去。享年55歳。久田道に墓がある
・平山意春
Ⓒ対馬全カタログ