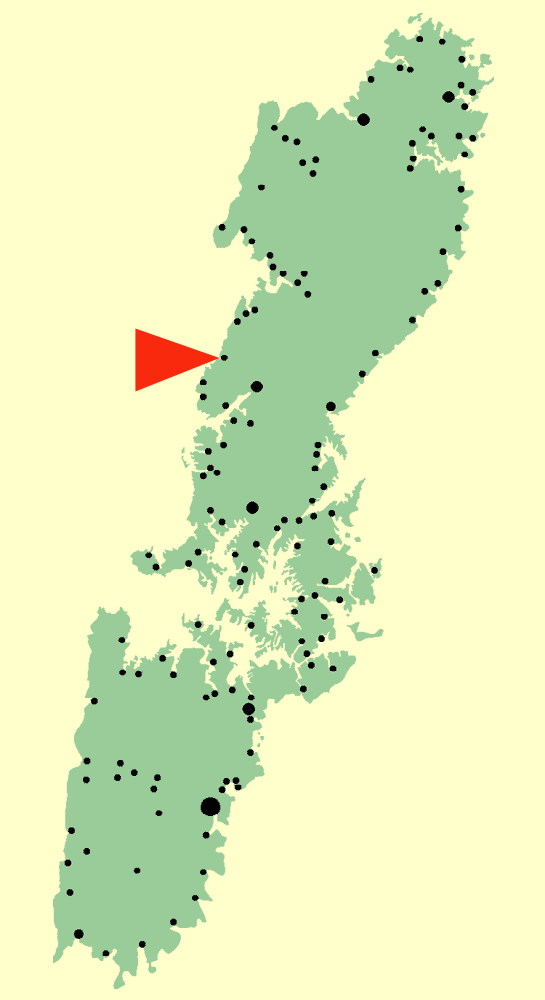2024年5月10日更新

峰町
津柳
【つやなぎ】
製塩には好立地だったが
農業や漁業には厳しい環境。
それを超えて今がある
かつての陸の孤島は解消されたが
対馬海峡に面する三方を山に囲まれた海付きの村。津柳を簡潔に表現すればそうなる。南隣りの青海には直線距離で約2km、北隣りの女連には直線距離で約2.5km、峰町の中心である三根にも約2.5kmと、周りのどの村からも遠く、山は険しく海岸は断崖絶壁。江戸時代は海が時化ると孤立する。まして冬ともなれば、「アナジ」と呼ばれる北西の風が吹き寄せ、寒い。車の通行できる道が開通するまで、生活するには厳しいロケーションだったようだ。
ただ青海や木坂と違い、小さいが自然の入江の奥にあり、昔から風や波を幾分だが和らげてくれる。今は埋め立ても進み、三重の堤防もある。もちろん道路も舗装され、1990年(平成2年)には津柳トンネルも完成し、三根にも10分ほどで出られるようになった。

津柳周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大等)
津柳の製塩は宗美濃介が起業か
1401年(応永8年)に、宗美濃彦六に、三根、佐賀、吉田、女連、津柳などの在庁の土地を給分として宛てがうという文書が残っており、宗美濃彦六が新たに津柳を治める侍として就任したことがわかる。
その30数年後の1434年(永享6年)、宗美濃介(そうみののすけ)に対して、津柳のわたくしの竃(塩竃)について料足300文は郡代官に払い、残る料足は免除すると、税金の一部を免除するという文書が発給されている。
宗美濃彦六と宗美濃介は同一人物と考えられており、宛てがわれた地に私設の塩竃を新たに作ったということだろう。塩竃新設の許可、税金免除の件といい、美濃介への特別な計らいがあるようだ。
宗美濃介とはどういう人物だったのか。青木和憲著『中世対馬宗氏領国と朝鮮』にその名があり、1402年(応永9年)、宗貞茂が宗賀茂の蜂起を鎮圧した時に、島主とともに戦い乱を鎮めた武将の一人だったということがわかる。
また、1431年(永享3年)から翌年にかけて、少弐氏から宗美濃介宛てに、島主宗貞盛の筑前への渡海(参戦)を催促する書状があり、宗美濃介が貞盛の側近であることがわかる。宗美濃介は貞茂、貞盛の2代に仕えた直臣だったのだろう。特別の計らいも首肯できる。
なお、宗美濃介の子孫はその後も栄え、1548年(天文15年)の改姓で峯氏となり、さらに佐伯氏に改め、仁位郷嵯峨の馬廻格給人として続いた。
200年近く続いた塩づくりにも翳り
鎌倉時代には全国的に製塩業が広がったが、その最大の要因は、大きな鉄製の釜が製造できるようになったことらしい。鎌倉後期になるとそれが筑前(福岡県)でも作られるようになり、一挙に九州一円で製塩が営まれるようになった。
海のそばで、わずかな土地と十分な燃料、つまり薪のもととなる森があれば、どこでも創業できる。製塩業はこの時代の先端事業だったに違いない。1471年の朝鮮の書『海東諸国紀』に、対馬は「四面は皆石山にして土やせ民貧し。煮塩・捕魚・販売を以て生と成す」と、対馬の産業のトップとして「煮塩」が挙げられている。
しかも津柳は、塩の売り先である朝鮮半島に近い。記録にはないが、中世の津柳は塩で潤ったのではないだろうか。
しかし、その繁栄には大きな代償が払われていた。竃の熱源として山の木々が伐られ、対馬の沿岸部ははげ山だらけになってしまい、16世紀に入ると対馬の製塩業が停滞、下降期に入り、世紀末にかけて次々と竃が閉じられていった。おそらく津柳の竃も同じ運命をたどることになったと想像される。
塩を作らなくなった津柳の江戸時代
津柳は江戸時代、少なくとも元禄から1850年(嘉永3年)までは給人がいなかったことがわかっている。塩竃のオーナーであった宗美濃介も宗貞盛の側近であったから津柳に住んでいたはずはなく、おそらく津柳は江戸時代の最初から最後まで給人不在の村だったに違いない。
室町時代は製塩で栄えた津柳だが、塩竃がなくなれば、漁業も交易も禁止された江戸時代は暮らしづらい村だったのではないかと想像できる。
江戸時代の津柳には、下記のようなデータが残されている。ここから当時の津柳の食料状況を考察してみる。
1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』
物成(ものなり)約33石、戸数15、人口(10歳以上)78、神社1、寺1、給人ー 、公役人5、肝煎1、猟師5、牛10、馬8、船4
1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』
籾麦150石、家17、人口87、男33、女38、10歳以下16、牛20、馬3、孝行芋1680俵
一人1日1.5合の麦
『元禄郷村帳』によると、1700年(元禄13年)の物成が33石なので、収穫量はその4倍の132石。その1/3が村人の食糧になるとすると44石、1年間一人(10歳以上)当たり0.56石、一人1日1.5合となる。これでも対馬の村の平均1.3合よりは多く、津柳の人たちは耕せるところは耕し、懸命に食糧増産に励んだようだ。
1861年(文久元年)には収穫量が1.12倍に増えたが、11歳以上の人口は71名と減少。1年間一人(11歳以上)当たりの食糧は0.7合と、1.25倍に。160年で少し増えたことになる。10歳以下も含めると1年間一人当たり0.57合となる。
ただ、1720年代からは孝行芋(サツマイモ)の栽培が盛んになり、木庭や山畑では蕎麦・粟・大豆に代って孝行芋が栽培されるようになっていった。その成果が1861年の孝行芋の収穫量1680俵で、津柳の人たちは孝行芋に随分助けられたのではないだろうか。
それと、5人の公役人全員が猟師だったというのも珍しい。鉄砲は沿岸防備の目的もあるが、猪や鹿などの肉の調達には欠かせなかったのかも知れない。
津柳では木庭作より山畑作が多かった
平地が少なく周りは低い山ばかりなので、津柳の人たちは山を焼いて木庭作を行ったり、山を耕して山畑作を行い、1700年頃は麦(大麦)をメインに栽培にしていたはずだ。
1671年(寛文11年)に作成された『物成帳』によると、津柳の物成の内訳は、畠方26.6石、木庭方6.6石、茶方0.1石で、合計33.3石となっている※。物成の合計が1700年と変わっていないので、元禄時代もその内訳はほとんど変わっていないと考えられる。
平地が少ないのに畠方の割合が8割と多いのは、谷沿いの緩やかな傾斜地や低い山の頂上周辺の平らな土地は山畑として活用したからだろう。
※『物成帳』に記載された物成量は、実際の収穫量から割り出した数値ではなく、収穫見込み量から計算したものなので長期間変わることはなく、その年の収穫量を知る根拠とはならない。
明治期までの津柳の漁業は採藻中心
津柳の海岸は、近隣の青海や木坂と違い、ささやかながらも入江になっている。室町時代初期、宗美濃介が製塩を始める以前、記録にはないが、漁業を営む人々が集落を作っていたかも知れない。
江戸時代になると藩は島民に漁業を禁止したが、採介漁は許されており、津柳でもワカメや海苔、ウニなどは採ったはずだ。一時、泉州佐野の漁民による鰯の地引網漁の請浦の一つだったが、漁果が芳しくなかったということだろう。1800年代には請浦のリストから除かれていた。
農業一辺倒の江戸時代が終わると、漁業解禁の明治。津柳でも漁業が盛んになるかと思いきや、そうではなかった。
1884年(明治17年)の『上下県郡村誌』をみると、津柳の舟数が3隻のみで、元禄時代の4隻より少ない。物産においても、海産物はスルメ200斤とワカメ1,800斤、甘海苔500枚だけだった。
東海岸の漁業に近い、津柳の漁業
峰町の村々は大正になった頃、やっと漁業に目覚め、志越、志多賀、佐賀、櫛、津柳、木坂、狩尾の7地区が、漁業という伝統的だが対馬では新しい業種に取り組むことになった。しかし、東海岸と西海岸では天候や漁場等の自然条件が違い、農業は西地区が収穫が多い“西高東低”なのにくらべ、漁業は“西低東高”になった。
豊かな漁場をもつ東海岸では水揚高も峰町全体の80%を占め、水産業が生業の中心になったが、西海岸では養殖や定置網の海面漁業や採介漁業が中心。その中にあって津柳だけが東海岸と同じように一本釣りをメインにした。
そんな津柳の漁港には立派な三重の防波堤が整備された。しかしそれでも、西からの風や波が強く、入出港時は緊張を要する。地元の漁港を利用するのは波の穏やかな6月から9月までで、それ以外は狩尾と三根浜の間にあるシビルに船を係留しているそうだ。

津柳漁港(2021年)

夕暮れ間近の津柳漁港(2003年)
平成の舟ぐろう大会で優勝したことも
津柳が漁師の村であることを再認識させたのが、1990年(平成2年)、三根湾で開催された「全島舟ぐろう大会」だった。峰町代表2チームのうち1チームとして津柳チームが参加し、優勝。対馬最強に輝いた。
さらにその3年後、峰町内の大会だが、ふるさと祭りのメインイベントとして開催された舟ぐろう大会で津柳チームが優勝した。
津柳では、戦前は3月21日の瀬祭りや、6月1日の乙宮神社の祭りで舟ぐろうを奉納したくらいで、戦後はほとんど行われなかった。木坂の海神神社で行われる舟ぐろう大会にも船が小さいので参加せず、どちらかというと舟ぐろうにそれほど積極的な村ではなかった。それが、全島大会で優勝するという快挙を成し遂げた。
漁師であっても、艪漕ぎ船自体がないので日常的に艪を漕ぐ機会はまったくない。つまり大会に備えて、体を鍛え、練習を重ねたはずだ。それには、勝利に対する熱があり、気合いがあり、体力もあった。そしてそれらを支えるベースとして、村の元気があった、のではないだろうか。
当時の津柳の人口は95人で、23世帯(1991年)。まだ色々な年齢層が揃っていた。2020年には世帯数は18だが、人口が36人になった。
【地名の由来】 1964年発行の『新対馬島誌』は、江戸時代の地誌『津島紀事』に書かれた「津柳」の由来を紹介している。津柳の地名が初めて歴史に登場したのが1374年(文中3年)だが、そこでは「つやなき(つやなぎ)」ではなく「つわなき(つわなぎ)」となっている。『津島紀事』の作者は、その「つわなき」の「つ」は「津」で、「わな」は「罠(魚を捕まえる仕掛け「魚梁(やな)」とも)」、「き」は「岐」で磯のことだと。ただ、どうしてそれがこの村の名前になったのかの説明がなく、説得力がない。
Ⓒ対馬全カタログ