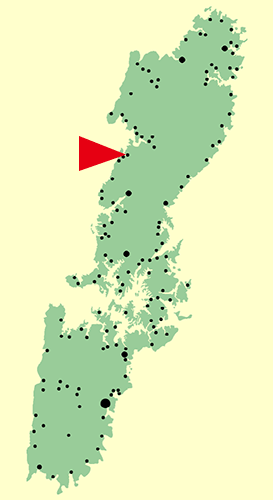2024年5月2日更新

上県町
鹿見
【ししみ】
西海岸北部の良港として
中世から交易を牽引。近年は
ノドグロ漁などの漁業が好調
おそらく弥生の頃から人の営みがあった
鹿見は上島西海岸のほぼ中央にあり、水深のある深い入江が特徴。湾を共有しながら山一つ隔てて隣接する久原とは兄弟地区のような関係だが、村の個性が少し違う。久原は農中心の半農半漁の村だが、鹿見は漁業中心の半農半漁だ。
また、久原には縄文時代の遺跡があるが、鹿見には縄文も弥生の遺跡もない。しかし、外洋の風波を防ぐ奥深い入江、恵まれた耕作環境。そして朝鮮半島からも近い。この地の利を考慮すれば、おそらく弥生時代以前から集落があったであろうと、多くの郷土史家が考えているようだ。
天然の良港を擁する村は中世の頃からは朝鮮半島との往来が活発で、1471年の朝鮮の書『海東諸国紀』では「是時未浦三十余戸」とあるのが当地とされている。

鹿見周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大、地名追加等)
室町時代には塩と魚で交易
鹿見の名が初めて文書に出てくるのが室町時代になってすぐ、南北朝が始まって2年後だ。
1340年(暦応3年)の「すへつな譲状案」に「ししに」とみえるのが鹿見と考えられており、鹿見の屋敷・畠などが「ためつなかくにいへ」に譲ると記されている。
また、1401年(応永8年)2月に当時の島主 宗貞茂が宗美濃彦六に発給した宛行状に、「対馬島内しゝみかま」という文言が見られ、鹿見に塩竃があったことがわかる。作った塩は獲った魚ととともに、主に朝鮮半島で麦や米に換えられていたはずだ。
さらに同年11月に、同じ宗美濃彦六に、三根、佐賀、吉田、女連、津柳の在庁の土地を給分として宛がうという文書も残っており、宗貞茂が宗美濃彦六家を厚遇していたのではないかと想像できる文書がある。翌年の宗賀茂の乱の戦いに、美濃彦六の息子と思われる宗美濃介が宗貞茂側の武将として参戦している。
島主と郡主による貿易商人取り込み合戦
1468年(応仁2年)、政治の中心は60年間“府”であり続けた佐賀から国府(数年後に「府中」に改名)に移ったが、経済の中心は港湾都市佐賀であり続けた。16世紀後半においても府中への物流は佐賀を中心とする経済圏に依存しており、朝鮮との貿易も府中の商人より、佐賀経済圏の商人たち(その正体は地侍)が活発だったという。(仁田、志多留、鹿見などの西海岸も佐賀経済圏を構成)
その100年後の1568年(永禄11年)、島主 宗義調によって鹿見在住の貿易商人 阿比留新七郎の神田重名義の通行権益の連年知行が認められている。さらに翌年には新七郎に「民部丞調常」という官途・実名を与えている。
これに対抗するように、1570年に伊奈郡主 宗調国は、新七郎と同族の人物に「民部丞国広」を与え畑地を給付。ところが1577年(天正5年)島主 宗義純は同じ人物に対して、「国広」という名を上書きするように「純広」を与えて改名させている。
この一連の発給合戦は、島主である宗本家が伊奈郡直轄化、佐賀経済圏の直接掌握をめざしたが故に起こったことで、この頃まで佐賀経済圏の貿易商人たちが力を持っていたことの証左でもある。
その結果は、1577年(天正5年)にすべての貿易商人たちが宗本家の在郷被官(家来)になり、勝負ありとなった。
その後、江戸時代になり兵農商分離、商人の府中一極集中が進むと、貿易商=地侍は、商いを諦めて在郷給人になるか、商人として府中に住むか、あるいは農民になるかを選択しなければならなくなり、鹿見からは商人が消えた。
朝鮮通信使が入港したことも
朝鮮半島の釜山や鎮海に近く、朝鮮半島との交易や交流には重要な役割を担ってきた。
朝鮮通信使の対馬初着は佐須奈か鰐浦と決まっていた時代に、一度だけ朝鮮通信使が鹿見に入港したことがある。1655年(明暦元年)6月、徳川綱吉の将軍襲職の祝賀に来日した通信使一行は、渡海時の気象状況が悪く(おそらく北東の風が強かったのだろう)、航路が予定より南へ寄ってしまった。
そのような場合の緊急避難用の港としては小綱が指定されていたが、大船団には本島と綱島との間の水道が狭く複雑すぎたのか。あるいは小綱まで航行する余裕がなかったのか。一行は、鹿見を選んだ。それは鹿見が大きな船団(488人)の入港に対応可能な風待ちの良港として、朝鮮の人々にも知られていたからに他ならない。

波穏やかな鹿見港
明治から昭和の初めにかけて、貿易港として繁栄
明治になって朝鮮との貿易額が年々増加するようになってきたため、朝鮮貿易も一般の外国貿易同様の取扱いを可能にするために、1884年(明治17年)に特別貿易港制度が導入された。特別貿易港では、朝鮮貿易における、日本人所有の船舶の出入りと貨物の積み卸しが可能になった。
当初は、博多港、門司港、厳原港の3港だけだったが、1890年(明治23年)に佐須奈港とともに鹿見港が特別貿易港として指定され、長崎税関鹿見出張所が設置され、1897年(明治30年)に長崎税関鹿見支署に。
そして、1899年(明治32年)には鹿見港が開港(貿易港)に指定され、海上交通時代の拠点として
1910年(明治43年)の韓国併合により、貿易港としての存在意義が失われ、1927年(昭和2年)に開港は取り消し、長崎税関鹿見支署も廃止された。その後は物流拠点として存続。
戦後になり再び対馬が国境の島になると、門司税関厳原税関支署の監視署が置かれたが、1967年(昭和42年)に廃署。現在、対馬には長崎県の重要港湾として厳原港が指定されているほか、地方港湾9港の中に比田勝、佐須奈、仁位などとともに鹿見港も入っており、地域の海上輸送網の一角を担っている。
浜田は開拓されても、農民、楽にならず
江戸時代、対馬藩は農業を振興するために、1671年(寛文11年)に田畑開発の奨励措置を決定し施行。1677年(延宝5年)には、さらに開発者のモチベーションを高めるために開発者優遇策を強化した。
1686年(貞享3年)、鹿見の給人・豊田長右衛門が自費で鹿見川の河口を埋立て、「浜田」を開いた。現在は田が埋立てられ住宅地となり、鹿見の中心地を形成している。
田畑開発奨励の一つとして、当時の開きによる耕作地は事業の主体者(ほとんどの場合、給人)の所有になるので、それは物成(年貢)の対象にはならない。
1700年(元禄13年)の物成51石から収穫量を計算すると204石。その1/3が村人の食糧になるとして※、68石。そこから村人一人当たりの1日の米麦量を算出すると、0.78合。その頃の対馬の平均1.3合の6割ほどだ。
その約160年後には収穫量が287石と、1.4倍に。人口は、元禄と比較するために10歳以下を引くと233人とほとんど変わっていないので、一人1日当たりの食べる量も1.4倍の1.12合。不足分を補ってくれる孝行芋もあり、大いに助かったのではないだろうか。
1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』
物成約51石、戸数36、人口238(10歳以上)、神社1、寺2、
給人4、公役人23、肝煎2、猟師18、牛24、馬10、船7
1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』
籾麦287石、家41軒、人口274人、男118人、女115人、
10歳以下41人、牛47疋、馬23疋、孝行芋2,980俵
※対馬藩の「物成(年貢)」は収穫量の1/4だが、それ以外に金銭で納める税金「公役銀」を工面するために麦などを売る必要があり、その他の支出も考慮すると、食糧として農民に残るのは収穫量の1/3くらいと考えられている。

江戸時代に干拓された「浜田」はさらに拡張され、宅地化が進み、現在は集落の中心に
江戸時代の漁業は、一時的な鯨漁と採藻
中世の頃は、塩と魚中心の鹿見経済だったが、江戸時代になると密輸を心配した藩が沖に出る漁業を禁止し、鹿見の人々は大打撃を受けた。藩は財政を潤すために、島外の漁師に運上金を取って漁を許可し、対馬の海は島外の漁師たちの漁場となった。
元禄の頃、平戸の金益組や、小値賀の小田六郎左衛門が鹿見の外浦である池の浦に、春先の上り鯨を狙う春納屋を置いたが、いつ始まり、いつ終わったのかの記録が見当たらない。
鹿見本神社の境内に鯨組から寄進された石灯籠があり、「元禄5年申年12月11日 平戸小値賀小田六郎左衛門」と読めるが、池の浦周辺に鯨組の墓がないことから推測すると、短期間だったのかも知れない。
江戸時代を通して島民が取り組めた漁業は、地先の磯の採藻や採貝、ウニ漁くらいで、鹿見は久原と違い佐野鰯網の請浦にはならなかったので、村網による地引網漁も遅れたと推察できる。
戦後すぐの鹿見の漁業は寄留中心
1950年(昭和25年)に、民俗学者宮本常一は初めて対馬を訪れた際に鹿見にも寄り、漁業を中心に取材したようだ。漁業の部分をまとめると、以下のようになる。
戦後すぐはまだ本戸と寄留(主に移住者)の区別が明確な時代で、鹿見は98世帯の内、本戸が41戸、寄留が57戸。寄留で本戸の土地と株を買い、本戸になった者もいる。寄留は農業以外のさまざまな職業に従事しているが、大半は漁業従事者だ。
村網として地引網があったが、今は寄留の人が持っている。また15尋四方の四ツ張網も同じ寄留の人が持っており、引き子は本戸寄留に関係なく希望者が引く。
寄留の漁業のメインは流し網漁で、魚の通り道に帯状の網を仕掛け、その網に刺さったり絡まったりした魚を捕獲する。刺し網漁とも言われており、トビウオが多くとれる。
漁業専業者は8軒で、いずれも動力船をもっている。5艘が流し網漁、3艘が延縄漁を行っている。
鹿見では寄留に寛大であった印象だが、宮本常一は「それは寄留者が多く入り込んでいるためである」と総括している。
21世紀はアカムツ(ノドグロ)の時代か
2004年(平成16年)に発行された『上県町誌』の漁業関連のページには、水揚げされる魚種として、イカ、ブリ、タイ、ヨコワ、シイラ、イワシ、アジ、サバ、カツオ、タチウオ、アナゴ、トビウオの名があった。これらの魚は比較的浅い水深域に生息する魚たちで、対馬の水産業は長い間、これらの魚種の水揚げだけで十分ともいえる漁獲量を誇ってきたとも言え、深い水域を積極的に狙うことはなかった。
一般的に「中深海」は水深200~1000mと言われているが、漁業・釣り用語としては120~300mの範囲で使われることが多い。そこは、アカムツ(ノドグロ)、クロムツ、アラ、アマダイ、キンメダイなどの高級魚と言われている魚が生息する、かなり魅力的な水域であり、対馬のいくつかの漁協は2005年(平成17年)頃からアカムツ漁を積極的に展開してきた。
アカムツ三大港と言われる、鹿見、小茂田、水崎では、水揚げ金額の8割がアカムツと言われている。
アカムツの魚体が傷つきにくい「地獄縄」を採用
対馬のアカムツ漁は魚体が傷つきにくい延縄漁(はえ縄とは、1本の幹縄に複数の針つき枝縄がついている仕掛けのこと)で行われるが、鹿見では延縄を改良し、さらに魚体が傷つきにくいようにした「地獄縄」採用している。
「釣りもの」、「底引きもの」、「刺し網もの」と、漁法で分けられ、漁法によって魚に対する評価、価格が違う。「釣りもの」は、延縄漁で獲る魚のことで、比較的魚体も大きく、傷が付くのは口だけで魚体の傷みもなく、輝いた状態で獲れるそうだ。鹿見港では水揚げされたアカムツには極力手を触れず、徹底した温度管理で鮮度を維持し、その中でも厳しい基準をクリアしたものを「紅瞳(べにひとみ)」と命名。東京の料亭や、高級和食料理店でも最高評価を得ている。
また、このアカムツ漁は家族の協力があってこそという。大漁時には水揚げ後すぐに出漁するので、携帯電話で縄の準備を奥さんたちに依頼。奥さんたちは言われた本数の枝縄の針に餌をかける仕事を再出港までに間に合わさなければならない。かなりの重労働だそうだ。
【地名の由来】「しし」は古語では「獣」の意で、「鹿」を「しし」と読むのは、「ししおどし」を「鹿威し」と書くように、古語の世界ではよくあるらしい。かつて鹿見周辺はが鹿や猪が多かったので、「しし満」→「ししみ」となり、「鹿見」になったという説が、江戸中期の郷土誌『津島紀事』に書かれている。それでは室町初期の古文書に「ししに」と表記されたことの説明がつかないが。また「鹿火」から由来しているという説もあるが、決定打がない。
Ⓒ対馬全カタログ