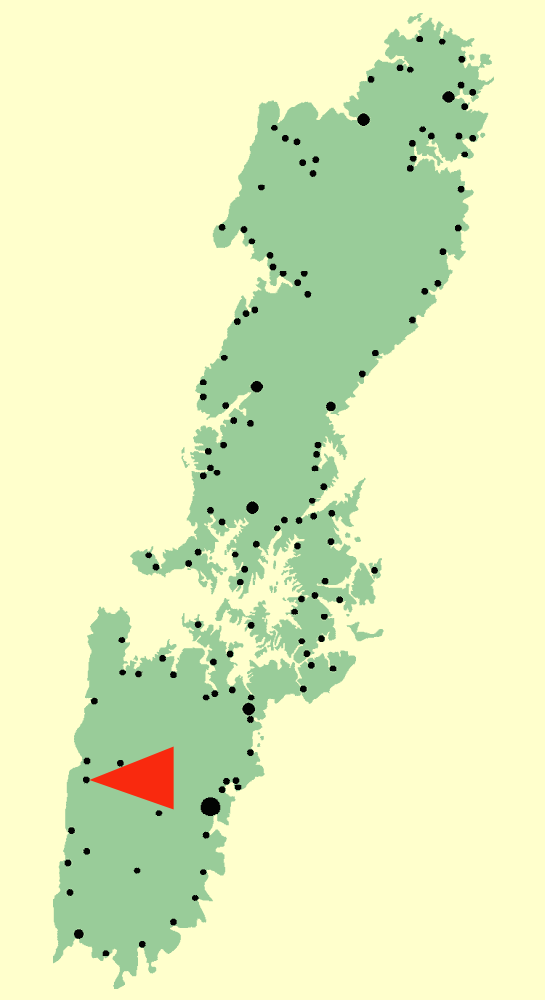2023年1月5日更新

厳原町
椎根
【しいね】
椎根は石屋根の美にこだわり
水に苦労しながらも
米の出来映えにこだわる
風土と政治と経済が生んだ石屋根
下島の中心である厳原市街から椎根まで、直線距離を測るとわずか9kmだ。しかし、椎根に行こうとすると、2016年に佐須坂トンネルはできたものの、小茂田経由ということもあり、厳原(市街)から30分はかかる。
対馬の西海岸は冬になると「あなじ」と呼ばれる北西の風が吹き寄せ、村々はそれに耐えて冬を越す。その強風に耐えるためにも重い石の屋根は非常に合理的であり、火事の際の類焼を防ぐためにも理にかなっているが、事情はそれだけではなかった。
まず藩は農民に瓦を許さなかった。明治になりさまざまな規制がなくなると、徐々に瓦葺きに変わっていったが、椎根では石屋根が続いた。明治の頃は石が瓦より安かったからかも知れない。
石屋根がいつの頃から普及したのか、明確な記録はない。1811年(文化8年)の佐賀藩の学者の「対馬日記」に石屋根の記述がはじめて登場することから、江戸時代中期から後期にかけてと推定されている。
1977年(昭和52年)、当時対馬で200棟以上もあった石屋根倉庫の中から、保存状態のよい椎根の石屋根倉庫が、長崎県の有形文化財に指定された。

初夏の椎根

秋の観光シーズン
石屋根の値段
母屋から離れた小屋は火事による被災を最小限にとどめることが目的で、300年以上の伝統があるらしい。昔は自給自足なので、衣類も食料も焼失すると大変な事態を招く。だから少々不便ではあるが母屋から離れて建てられ、そこに什器や衣類を保管し、食料を備蓄した。湿気とねずみによる害を防ぐために高床式で、村によって床の高さが違ったりするらしい。
石屋根には対馬のどこでも手に入る頁岩(けつがん)=泥板岩を使用する。ただ立派な石屋根を望む場合は、浅茅湾の中央に位置する島山の頁岩を使用する。1985年(昭和60年)に行われた、文化財指定の石屋根の葺き替え工事経費は700万円だった。もちろん今は瓦の方が安い。
石の総重量は200トンもあるという。葺き替えは村中総出で行われたそうだが、葺き替え技術の継承は大丈夫なのだろうか。椎根にはかつて30棟の石屋根倉庫があったが、2022年には6棟になってしまった。
石屋根は、椎根のほかに久根浜、久根田舎に比較的残っている。こちらは観光客が訪れることもなく、時の重みに少々くたびれた石屋根倉庫が当たり前のように道路わきに建っている。

2022年現在、椎根の石屋根倉庫は6棟 (この写真では5棟)
史料の少ない古代から中世
椎根周辺には古代の遺跡はないが、椎根川の中流の恵比須社に11個の凹み石が祀られていたらしい。この石が縄文時代の遺跡から出土例の多い石器らしく、縄文時代、椎根周辺に人が暮らしていた可能性があるそうだ。しかし、その後の遺物は発見されていない。
1471年に発行された韓国の書『海東諸国紀』に、佐須4浦300戸と記されているが、4浦の中の1つは椎根に違いなく、さらに1540年頃に椎根を安堵した文書が存在することから、中世も人の営みがあったようだ。おそらく元寇で侵犯された歴史も、小茂田など、ほかの佐須の村と同様と考えられている。
江戸時代、戸数・人口はほぼ横ばいだが、
生産高は1.38倍に
生産高は1.38倍に
江戸時代の対馬の村々の暮らしを推測するデータとして、1700年(元禄13年)の『元禄郷村帳』と1861年(文久元年)の『八郷村々惣出来高等調帳』がある。椎根のデータは下のようになる。
1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』
物成約95石、戸数48、人口220(10歳以下含まず)、神社1、寺1、給人2、公役人24、肝煎1、猟師10、牛15、馬41、船0 ※「物成」は年貢のことであり、対馬では生産高の25%
1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』
籾麦514石、家49、人口279、男109、女119、10歳以下51、牛45、馬135、孝行芋720俵
このデータから、元禄時代の椎根は、一人当たり約1.3石の米麦を消費していたことが推測でき、対馬の郷村平均は一人当たり1.1石だから、平均より豊かだったことがわかる。また幕末期には米麦の生産高は1.38倍になり、一人当たりの米麦も約1.7石に増えている(子供も含めると1.4石だが)。開拓で農地を増やし、余裕も生まれてきたことが想像できる。
また、生産高を増やした村の中には、家数が増えた村もあるが、椎根の家数はほとんど変わらず、人口もほぼ横ばいだ。家数が増えた小茂田、樫根、今里などに比べ、「家」に対する考え方が保守的だったのかも知れない。

集落より海側の田畑の多くは開拓によるもの
(○は石屋根倉庫)
(○は石屋根倉庫)
比較的余裕があった?! 椎根経済
1650年(慶安3年)、藩主が椎根川上流の山中における銀山開坑の願い出に許可を与えた、という記録が残されている。それから100年間銀山は続いたそうだが、それで村が潤ったかどうかはわからない。
1884年(明治17年)の『上下県郡村誌』の学校の項に、公立小茂田学区椎根分校/生徒男12人、女12人、とある。この時代に男女同数の生徒がいる学校は他になく、女性の教育にも熱心だったことがわかる。この地区の進取の気風を語る好例だ。それは椎根が、対馬の中では比較的余裕のある村だったということかもしれない。
同じ郡村誌で、物産として、米107石(中等)、大麦220石(中等)・・・とある。対馬としては量・質ともに素晴しいといえるだろう。それを可能にしたのが、椎根川下流域の埋め立て・開田・圃場改善で、木庭作が多い対馬の中では珍しく収穫量も多く、それが“比較的余裕”のベースだったのではないだろうか。

椎根の集落
農業用水の確保に苦労
実は、“比較的余裕”の経済とは裏腹に、椎根は水に苦労した村だった。椎根川の水量は少なく、堰をつくり川の水を引いたのは河口近くの左岸(東側)、東塩屋と呼ばれる一帯だけ。すべての田が川から水を引くことは不可能だった。
そこで椎根の人々はそれぞれの田の隅に縦横2~3メートル、深さ4~5メートルの大きな井戸を掘り、そこに水をためて、田に水車や桶で水をまわした。この農業用の井戸は「ホナ」と呼ばれ、椎根の米作りには欠かせないものだった。
そのホナに時々子供たちが落ちたからだろうか。現在、椎根にホナはない。南隣の上槻に1カ所、さらに南の久根田舎には数カ所、ホナに蓋をしてポンプを設置した現代版のホナを見ることができる(2022年)。

ポンプを設置した久根田舎の現代版ホナ
【地名の由来】 山を越えて隣村となる「樫根」と対をなすような地名であり、どちらも食用となる木の実を産するところも同じ。椎が多い所、樫が多い所ということを地名にしたかったのだろう。「島根」という地名の由来に、島国だから「島」、それに接尾語の「根」をプラスしたものという解説もあるので、椎根の「根」も接尾語「根」ではないだろうか。接尾語「根」の例:屋根・羽根・垣根
Ⓒ対馬全カタログ