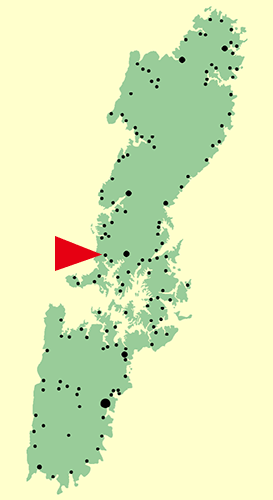2023年8月4日

豊玉町
佐保
【さほ】
海、山の幸に恵まれた村は
幕末期の二重公役を乗り越え
過疎にも柔軟に対応
付近一帯は遺跡の宝庫
仁位浅茅湾から西北に深く切れ込んだ佐保浦の沿岸には、弥生時代の遺跡が多く、佐保が弥生時代以前からの村であることを語っている。浦口から列記すると、ソウザキ遺跡、唐船遺跡、佐保浦赤崎遺跡、クロキ南鼻遺跡、唐崎遺跡、キロスガ浜遺跡、イノサエ遺跡、シゲノダン遺跡となる。この中で特に貴重とされているのが、シゲノダン遺跡ではないだろうか。
長崎県の公式ホームページ内「遺跡大辞典」には、シゲノダン遺跡の説明として次のように書かれてある。
「遺跡は佐保川西側の丘陵先端部に位置する。1974年耕作中地主によって偶然発見された。遺物の配置状況について九州大学が聞き取りを行った結果、何らかの遺構に伴うもので無く、露出状況であった事から埋納遺跡である可能性が指摘された。土器の出土が無いことからはっきりした時期比定は出来ないが、貨泉(古代中国の銅銭)や舶載青銅器、国産の中広銅戈の特徴から弥生時代後期の可能性が高い。なお、遺物は国が発見者から直接買い上げ、現在国立歴史民俗博物館に収蔵されている。」
「埋納遺跡」とは、保管のためにそこに埋めていたものが発掘されたということ。いつかの時代、どこか付近の遺跡の出土品がそこに埋められていた、ということかも知れない。レプリカが豊玉町郷土館に展示されている

佐保周辺地形図:西側の海岸も佐保地区。そこで採れる藻が肥料となり、豊かな田畑をつくった 出典:国土地理院地形図(村名・地名拡大、遺跡・史跡を記入)

佐保地区の中心集落
水田稲作の村は開田も早かった
中世の佐保は、室町時代の朝鮮の書『海東諸国紀』に戸数200余戸とあるように、数字自体は少々過大ではあるものの、それなりに大きな村だったようだ。浅茅湾内のいくつかの村がそうであるように海外通交の拠点の一つだったと言われている。
佐保のことは『豊玉町誌』に詳しく載っている。約40ページにわたって語られていることの多くは江戸時代のエピソードだ。
まず、江戸時代に佐保は開き(干拓)が盛んで、開田は仁位郷の中心である仁位よりも早かった。その要因の一つに対馬ではまだ木庭作中心の14世紀初頭に、すでに佐保では水田で米を作られていたことが挙げられる。
1671年(寛文11年)から始まった佐保の開田事業は、1677年(延宝5年)に発せられた開田期間中の税免除を含む新令によってさらに拍車がかかった。
160年で、さらに収穫量を1.4倍に!
元禄時代までに開田によって収穫量をかなり増やしたであろうと思われる佐保だったが、1700年(元禄13年)の物成(年貢)は約69石。収穫量を計算すると69×4=276石で、村に残る量を人数で割ると、1.48石。その頃の対馬の郷村平均の1.1石よりは多いが、周辺の村に比べて特に優れた数字ではない。
しかし、その161年後の1861年(文久元年)のデータでは、収穫量が1.4倍となり、一人当たり2.32石(元禄とのデータを揃えるため11歳以上の人口で計算)。対馬では上位の数字となる。
面積と収穫量が正比例すると仮定すると、耕作地面積が1.4倍に。江戸時代に生きた佐保の人たちの頑張りが想像できる。
1700年(元禄13年)『元禄郷村帳』
物成約69石、戸数30、人口(11歳以上)140、神社1、寺1、
給人2、公役人15、肝煎1、猟師7、牛27、馬7、船5
1861年(文久元年)『八郷村々惣出来高等調帳』
籾麦388石、家32、人口152、男72、女53、10歳以下27、牛27、馬21、孝行芋1,850俵

佐保浜の開きによって干拓された農地
「海で半年、山で半年」の村
「海で半年、山で半年」の“山”というのは、木庭作中心の対馬では多くの場合“農業”を意味する。前述のように佐保は農業の村であったが、漁業も、主に採藻だが、朝鮮海峡に面する西海岸には広大な磯場を持ち、海産物が豊富に採れた。
さらに佐野網の請浦*でもあり、配分として収穫量の3分の1の鰯を得て、それを干鰯(ほしか)とし、麦の肥料とした。この海と山(陸)の好循環がこの村の強みだった。
実際に1884年(明治17年)の『上下県郡村誌』でも、米は53石で豊玉では仁位に次いで2位、ワカメは8,316斤で千尋藻に次いで2位だった。
※大阪の泉佐野から対馬にやってくる地引網漁船団に浜を貸し、藩への運上銀の納入を代行するなどのサポートも行い、報酬を得た
藩支配ではなく地頭支配の地頭村に
文政4年(1821年)、佐保は公領地ではなく、暢孫(ながつぐ)家の私領「地頭村」となった。その初代地頭となった暢孫志摩は藩主宗義質(よしかた)の異母弟で、世継ぎ紛争を避けるために宗籍から離脱して家臣となることを表明。藩主からその見返りとして、「暢孫」という名字とともに、佐保村を知行地として与えられた。
領地内の百姓はすべて地頭の支配下に組み込まれ、年貢や公役銀は地頭に納めることになった。これだけならいいのだが、何故か藩の公役は免除されないまま、地頭家への日々の納め物や地頭から課せられた労働が加わった。つまり、二重公役。百姓たちにとっては災難でしかなかった。
廃藩置県が施行される明治4年(1871年)までのほぼ50年間、佐保は仁位郷で唯一の地頭村であった
かつて奴加岳村の中心として
1908年(明治41年)4月から、沖縄県及び島嶼町村制が施行され、対馬は2郡1町12ヵ村に分けられた。元豊玉町区は「仁位村」と「奴加岳村」に分けられ、奴加岳村の村役場は佐保に置かれた。
上島の浅茅湾沿岸は、位置的にみて中央部の中心は仁位が、西部は佐保が適当と判断されてのことだった。発足当初の奴加岳村の戸数は378戸、人口は2,280人で、ほぼ仁位村と同等だった。
奴加岳村の村名は、応永の外寇時に、朝鮮軍の侵攻をはね除けた「糠岳の合戦」の古戦場にちなんだもの。また、1917年(大正6年)には村役場前の佐保川に、役場の存在感を高めるかのような、当時としては立派な石橋「佐保橋」が架けられた。
1955年(昭和30年)3月の豊玉村誕生まで47年間、佐保は奴加岳村の主邑として、上島浅茅湾沿岸西部の中心として機能した。

奴加岳村役場跡と記念碑(左下)

佐保橋:佐保橋はコンクリートの下になってしまい、橋脚は一部コンクリートで補強されたが、現在も人や車両の通行を支えている
シゲノダンと奴加岳高等実業青年学校
大正末期から昭和の初め頃まで、日本全国で青年団活動というのが盛んだったそうだ。その頃、佐保およびその周辺の村々の青年たちは、農閑期・漁閑期を利用してシゲノダンに集まり、丘の上に自分たちのための広場、運動場を作った。
その運動場で何が開催されたかは記録に残っていないが、その後、鈴江青年学校の宿泊訓練所として活用され、1941年(昭和16年)には奴加岳高等実業青年学校がそこに創立された。
青年といっても1年生は尋常小学校を卒業したばかりの12歳。高等小学校や中学校に進学せず働くことを選んだ青少年に対して、社会教育や農業補習、水産補習などを行ったそうだ。

現在のシゲノダン:戦前、ここに奴加岳高等実業青年学校が建てられた。現在は「佐保生活感」が建ち、地域コミュニティの中心となっている
かいえとうと、鶏悼碑
「かいえとう」とはなかなか聞かない名だが、おそらく対馬ではここだけにあるのではないだろうか。シゲノダンの広場の一角に建っている。
「かいえ」は「海合」で、「とう」は「塔」だ。「海会」は法華経の教えで、すべての川の水が最後は海で会うように、すべての人(命)も最後に帰るところは同じである、ということ。
この塔のフルネームは「法華一字一石海会塔」。「法華」は法華経のこと。「一字一石」は、お経の一字一字を小さく平たい石に筆写する写経のことで、字の書かれた石「経石」を土中に埋めて経塚を建て、写経の完成とする。『豊玉町誌』には江戸時代に流行ったと書かれているが、対馬の他の村では見かけない。
碑には、「三世諸仏 出生本懐 歴代諸祖 無窮命脈」と彫られてある。「すべての人が自分の本懐(何のために生まれてきたか)を知り、つまり悟り、命が無限に受け継がれていきますように」という意味ではないだろうか。
また、シゲノダンの下(東斜面)には、養鶏場で飼育され人の命の糧となった鶏を悼む「鶏悼碑(けいとうひ)」が建てられている。養鶏業者らしき人たちが時々手を合わせにくるという。

法華一字一石海会塔

鶏悼碑
校名の変遷が時代を表わす、鈴江小学校
仁位方面から佐保をめざすと、佐保地区に入る直前の左側に何も建っていない広場が目に入ってくる。ここが1902年(明治35年)から1974年(昭和49年)まで続いた鈴江(すずえ)小学校跡だ。
鈴江小学校は1902年(明治35年)に佐保村字鈴江に鈴江尋常小学校としてスタートした。1922年(大正11年)に鈴江尋常高等小学校、1941年(昭和16年)に奴加岳村立鈴江国民学校に改称され、戦後、1947年(昭和22年)に奴加岳村立鈴江小学校となった。
1955年(昭和30))、仁位村と奴加岳村の合併によって豊玉村が発足すると、豊玉村立鈴江小学校に改称。1974年(昭和49年)、統合により閉校された。
木造校舎が残されていたが2012年(平成24年)までに解体され、今は門柱だけが残っている。

鈴江小学校跡
耕作放棄地が見当たらない村
江戸時代、農地の開発が早かった佐保は、元禄の頃には当時の対馬の村としては多めの生産量を誇った。しかし、それでも暮らしには余裕がない。江戸時代の佐保の人たちは必死に土地を増やし、収穫量を増やしてきた。幕末期には収穫量が元禄期の1.4倍になった。
最近ではそんなかつて先祖が開発した農地を持て余す村が増えてきている。過疎化、高齢化が原因だが、対馬でもかつての美しい田園風景を失ってしまった村は多い。
但し、佐保においては上空からの写真を見てもわかるように、水田や畑は美しい緑で覆われている。ビニールハウスも9本もあり、しっかり農業が営まれている(2022年現在)。対馬では貴重な、過疎化にうまく対応している村といえそうだ。

海岸に近い浜の方では新たな取り組みが行われている
【地名の由来】狭い浦=狭浦を「さほ」と読んだのではないかという説が有力。確かに佐保浦は狭い。「狭」は「狭山(さやま)」などの地名で知られるように「さ」と読まれ、「浦」は音読みで「ふ」「ほ」と読まれる。対馬では「浦」を「ほ」と読む例が多いそうだ
Ⓒ対馬全カタログ