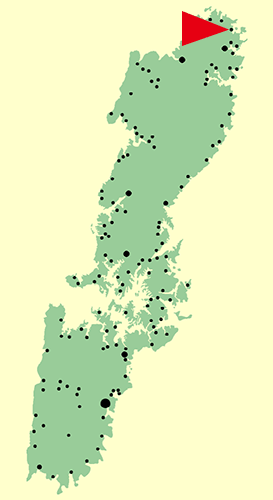2023年7月8日更新

上対馬町
泉
【いずみ】
はるばる大阪から
秀吉に連れられてきた
泉佐野漁民の拠点。泉
村の名を変えるほどの力とは
弥生時代前期の遺跡から石剣や甕棺が発見され、古くからの村であったことがうかがえる。15世紀後半の韓国の書『海東諸国紀』には「時古里(しこり)」の名で20余戸とある。その約100年後の天正の頃には16戸だったと資料にあるが、その時点での村名は明らかでない。1700年の郷村帳には「泉」として登場し33戸となっている。
泉は、大阪の泉佐野の漁師の最初の拠点といわれている。「泉」という地名が「泉州」からきているのは容易に想像できるが、旅人漁師の漁の拠点というくらいの理由で村の名が変るとも思えない。
秀吉からの恩賞の一部か
泉佐野の漁師たちはブリやイワシを求めて、室町時代の中頃から対馬近海に来ていたと言われている。また、大阪近辺の漁民たちは豊臣秀吉によって戦さにかりだされ、水夫として活躍していた。泉佐野の漁師が朝鮮侵略の際の大いに重宝されたのは容易に想像できる。常は日々の食料調達に働き、ある時は釜山と対馬、九州を行き来する往復御用船として活躍したに違いない。
その功が秀吉に認められ、その恩賞として年に銀300枚の運上金だけで、対馬の62浦(ほぼ全浦)での地引網(イワシ漁)の漁業権を保証されることになった。そして、出先としてこの地に定住する者も増え、あくまでも想像だが、おそらく「泉」への地名変更もその恩賞とセットか、村のさらなる繁栄を願っての島主あるいは地元からの申し出だったのではないだろうか。
佐野網の盛衰
佐野の漁師たちの地引網は佐野網と呼ばれ、漁獲の対象は鰯(いわし)だった。室町末期から都市近郊の農家は、増産のために肥料を積極的に使うようになり、鰯を干した干鰯(ほしか)は最高の肥料として需要が増大していった。
資本は和泉の廻船問屋や干鰯問屋が出し、往路は米、塩、紙、綿、たばこ、畳表などを積み、復路は干鰯や塩魚を積んだ。運上金を払い逗留切手をもらうために、まず府中(厳原)に入港するのだが、年間500~600艘が来島した。
しかし、元禄以後は入漁制限が厳しく、手続きが煩雑になった。元々の運上金が高価だったこともあり、経営が難しくなってくると、佐野網も次第に減少していった。
慶長の役から213年後の1810年(文化7年)の記録では、権利が存続していたのは62浦のうち37浦。その中には泉の名はない。ほとんどが府中から近い、島中央部の東西両岸や浅茅湾の浦だった。
漁場の移動
佐野からはイワシを獲る網船だけでなく、延縄でブリ漁を行う縄船も対馬に入漁していた。沖合いで漁をする縄船に関しては、江戸時代初期から潜商(密貿易)を警戒して乗り入れ禁止地区を設けられ、その後に佐野の縄船は泉より15kmほど南の琴(きん)浦を北限にした、南北約20kmの海域に漁場が限定されてしまった。
地引網、延縄漁ともに、その漁場の移動により、泉は佐野漁師の拠点としての役割を失ったが、その地名と、佐野が本籍と思われる数軒の苗字(「辻」「和田」など)だけが、その名残をと どめているという。

泉の午後 (2003年)
村を守ってくれる志古島
泉湾に蓋をするように浮かんでいる島が「志古島」で、泉湾はかつては「志古浦」、村名は志古の里と書いて「志古里」だった。シコは矢筒のことらしく、村を守ってもらうことを祈願し、矢筒を供えて志古嶋大明神を祀ったのではないか、とも言われている。
明治期に村の中央に位置する旧家の裏から石剣と土器が発見され、すぐ近くから縄文時代晩期か弥生時代初頭かと推される箱式石棺が見つかった(泉遺跡)。対馬の北端部ではもっとも古い遺跡の一つだ。
志古島が湾内を隠してくれ、平地もある。ここは古の人々にとって住みやすい、あるいは安心して住める地形だったのではないだろうか。
現在、 志古島神社は、九州で小弐氏とともに戦い最期を遂げた宗盛国、盛世を祀っている舌崎神社とともに、壬(みずのえ)神社に合祀されている。

志古島

志古島神社が合祀されている壬神社
対馬を代表する植物、オウゴンオニユリ発生地
100年以上前に上県町女連で発見され、対馬を代表する植物として知られるオウゴンオニユリ。オニユリの突然変異種だが、世界で対馬だけに出現したと言われている。
そのオウゴンオニユリが1963年(昭和38年)頃に泉でも発見された。こちらのオウゴンオニユリは女連産にくらべ花弁の斑点が小さいそうだ。

泉系のオウゴンオニユリ。上県町女連系に比べ斑点が小さい 写真:國分英俊氏
【地名の由来】 中世の頃までは地名は「志古里(しこり)」。それが「泉」になったのは、やはり泉佐野漁民の拠点となったからか。
Ⓒ対馬全カタログ