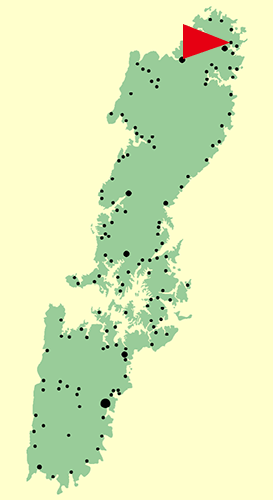2020年7月31日更新

上対馬町
古里
【ふるさと】
歴史に登場することの
少ない穏やかな村。
その名も古里
遺跡はどちらの村のもの?
遺跡の存在により、古里が弥生時代以前からの村であることは明白とされている。1971年(昭和46年)に箱式石棺4基が発見され、塔ノ首遺跡と名付けられたその遺跡の出土品には、九州産土器や広形銅矛を中心としながらも、半島産、中国産の土器が混じっており、海を越えて広く交流があったことを今に伝えている。
現在は古里の遺跡として紹介される塔ノ首遺跡だが、実は西泊に拠を置いて交易で活躍した豪族のものではないかという説が有力だ。古里の本村が遺跡から離れているのに比べ、西泊の字である田ノ越は塔ノ首のすぐ東であることが主たる理由となっている。しかし、弥生時代の墳墓は在所よりは海に近い、村から離れた岬につくられることが多い。“塔ノ首”もかつては岬。古里の中の一派が交易をはじめ、それに最適な場所をもとめて“塔ノ首”を越え、西泊の集落をつくったとは考えられないのだろうか。
なお、塔ノ首遺跡は1977年(昭和52年)、国指定文化財に登録されている。

塔ノ首遺跡
地道に頑張ってきた村
1311年(応長元年)の文書に古里浦の名が見られるが、1471年の朝鮮の書『海東諸国紀』には古里はなく、東隣りの西泊と南隣りの比田勝が、それぞれ100余戸、50余戸として記載されている。古里は深い入江の奥にあったので、もれてしまったとも言われているが、交易と漁業が中心の西泊に比べれ、古里は農業主体の村。外からは興味を持たれない地味で地道な村だったのではないだろうか。
元禄時代は戸数9、人数26(10歳以下は含まず)。明治7年頃は戸数11、人数76。元禄時代の10歳以下の子供数を10と仮定して比較すると、約180年間で人口は2倍に増えたことになる。つまり1家族4人から1家族7人が養える村へ。開田などによる着実な生産性の向上が、少しずつこの村を豊かにしていったようだ。
比田勝のベッドタウンに
おそらく今の古里からは、かつての静かな農村というイメージは想像できない。その転機となったのが、塔ノ首遺跡が発見された年、つまり1971年だった。その年の7月に上対馬町は集中豪雨に襲われ、この村の中心を流れる古里川は氾濫。川岸や橋に大きな被害をこうむった。そしてその補修工事に続いて宅地造成が行われ、この地区の景色は大きく変わっていくことになる。
現在は公営住宅をはじめ多くの住宅が建ち、比田勝のベッドタウンとして賑わっている。

塔ノ首遺跡からの眺望:向う岸は西泊地区
【地名の由来】 隣り村・西泊のかつての在所で、古い方の里だから古里と呼ばれていると『新対馬島誌』にあるが、古里村の本拠と西泊村の本拠は別とされている。そこでシンプルに西泊村より古い里だからと考える説もあるが、『新対馬島誌』の説が無理がないように思う。
Ⓒ対馬全カタログ