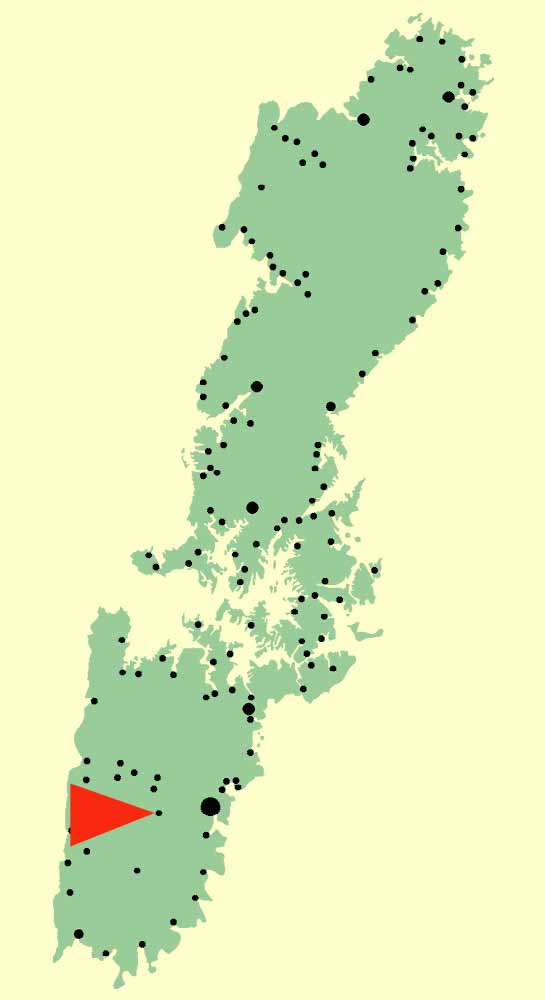2024年8月1日更新

厳原町
日掛
【ひかげ】
村の起源は銀山用黒炭だが、
後に白炭にシフト。そして
今は対州そば在来種栽培地
対馬では珍しい山の中の村
日掛は対馬では唯一の山の中の村。山に囲まれていることは内山と同じだが、盆地で周辺には田畑が広がる内山に比べ、日掛は谷川に沿って家が点在する、まさしく山間(やまあい)の村だ。
かつてはこの周辺で製炭が盛んだったため、この辺り一帯を「炭山」と呼び、日掛集落のことも俗に「炭山」と呼んだ時代もあったそうだ。
縦に長い集落だが一部は日掛川(佐須川)を挟むように家が建ち、右岸(上流から見て右)を陽(ひなた)と呼び、住所は下原。左岸を陰(かげ)を呼び、住所は樫根となっている。

日掛周辺地図 出典:国土地理院地形図(地名拡大、地名追加等)
白炭をつくるためにつくられた村か
日掛の歴史について調べようとしても、郷土誌関連本では見つけることはできない。現地に取材すると、幸い90歳を超える老媼(ろうおう)に話を伺うことができた。
江戸時代に対馬藩は、島根、千葉、京都など島外から6軒を呼び、白炭づくりに当たらせようとしたが、対馬(藩)の事情を理解している人間も必要ということで、まとめ役、管理者として府中から1軒が派遣された。それが田中家(現在の原野家)で、給分は士富の水田2反7畝。
田中家は在郷給人ではない。府中に籍のある府内士だ。その田中家を加えた7軒がその後も“本戸7軒”として継がれていった(おそらく田中家が本戸に加わったのは明治後だろう)。
入植した直後は藩が白炭製造の指導者として呼んだ豊後(大分)の製炭技術者がいたが、伝え終わると豊後へ帰ったという。その後、田中家が管理者として加わっることになったという。入植者たちは、川のそばに掘立て小屋を建てて雨露をしのぎ、冬の寒さにも耐え、炭づくりに精を出した。
これが老媼が母親から聞かされた日掛の歴史だそうだ。
日掛の白炭は佐須銀山用ではなかった
1884年(明治17年)『上下県郡村誌 』では、日掛地区を含む下原のデータとしてだが、物産として木炭3,000斤が記載されている。品質は上等と書かれており、内山の木炭(下等)とは評価に大差があり、これが白炭をさすことは容易に想像できる。
日掛の白炭は、佐須銀山の精錬用に高温を発する炭を必要とするところから生産されるようになったという説もあるが、どうもそれは違うようだ。備長炭のような高級な白炭は安土桃山から江戸時代初期に開発され、それが全国に普及するのは江戸時代中期、元禄以後からで、佐須銀山の盛期(江戸時代初期:1600年代後半)とは重ならない。
また、江戸時代に日掛の炭焼きの管理役を任ぜられた田中家の記録では、明和、安永の頃(1770年前後)に亡くなった先祖は府中に住んでおり、その後裔が藩に命ぜられて日掛に転任(移住)したことになっている。1737年(元文2年)に閉山となる佐須銀山の炭を焼いたとは考えにくい。
また、日掛の人々は、自分たちの作っている白炭は刀鍛冶に使われると聞かされ、それが語り継がれてきた。対馬藩でどれだけの刀が作られたかはわからないが、おそらく他藩にも輸出され藩の外貨獲得、財政改善に貢献したのではないだろうか。
※白炭は奈良時代から製造されたが、叩けば金属音がする備長炭のような「堅炭」ではなく、火力も備長炭などにくらべれば劣った。
宮本常一の聞いた話は少し違う
1951年(昭和26年)に“歩く民俗学者”として有名な宮本常一も日掛を訪れていた。彼も村人に話を聞き、この村の成り立ちを文章にしていた。
「ここにはじめて住みついたのは石見(島根県)から来た者で、対馬樫根にあった銀山の炭を焼くためであったという。(中略)石見から来た家は36軒であったという。そしてそのはじめは、山中にバラバラに家をたて、家のまわりの木を伐って炭を焼いた。いまでも炭を焼くために山を伐っていると屋敷址や古い墓があるという。
しかし銀山への事業がやんでからは厳原の町の炭を焼くようになり、人びとも厳原へ出るのに便利な日掛に住むようになった。」(『私の日本地図(15)壱岐・対馬紀行』より)
宮本常一が書いた日掛に関する文章の中には「白炭」という語がない。白炭以前の村の歴史ということになる。前述のように備長炭のような堅炭の白炭は江戸時代初期にはまだ普及しておらず、その製炭技術が対馬に至ったとは考えにくい。宮本常一が聞いたのは白炭以前の日掛の歴史と考えるべきだろう。

宮本常一が撮影した、まだ炭を焼いていた頃の日掛。炭焼きのためか、焼畑のためか、木が茂っていない(昭和26年) 写真提供:宮本常一記念館
あくまでも仮説だが・・・日掛の歴史
銀山で鉱石から銀を取り出し純度を高めていくには精錬を繰り返すが、そのためには膨大で強力な火力がいる。それには薪ではなく炭が欠かせない。その炭を安定供給するために、藩は銀山再開と同時に、日掛を含む佐須の奥山に大勢の炭焼きを入れた。その主力が石見銀山のある石見(島根)の人たちで、36軒あった。その他に、京都や千葉からも入植した。
その後、銀山が下火になる頃に、対馬藩では8,000人に膨れ上がった島外人(銀山関係では多かった1678年で約1,349人)を送り返す政策がとられたこともあり、1737年(元文2年)の銀山の閉山後は数少ない炭焼きが、府中へのアクセスに便利な日掛周辺に残るのみとなった。
18世紀中頃にはそれが6軒のみになり、藩は新たに刀鍛冶用に白炭を焼かせようとし、豊後から製炭技術者を呼んだ。その後、白炭生産は軌道に載ったが、対馬の事情に疎い島外人だけだったので、藩や府中とのやりとりの円滑化等をめざし、まとめ役、管理者として田中家(現在の原野家)を日掛に派遣した。
あくまでも仮説だが、それほど的からは外れていないのではないだろうか
。
白炭づくりは1960年頃に終了
白炭をつくるには、まず時間をかけて低温で炭化する。工程の終わりに窯の中を1000℃前後の高温にし、真っ赤に燃えさかる炭を窯から掻き出して素灰をかぶせてすばやく冷やす。その窯出しの際の熱さが強烈で、最悪の労働環境とも言える。江戸時代のように、生きるために白炭を作るしかないのであればできる仕事だが、他に選択肢があるとなかなか選びづらい職業だ。
田中家も江戸時代は管理者だったが、明治になると白炭を焼いて暮らしを立てるしかなかったそうだ。老媼も若い頃に炭焼きを手伝ったそうだが、窯出しの時の熱さは火傷するかと思うほどだったという。
明治中頃から対馬では全島規模で白炭製炭の普及が図られ、「対州白炭」として関西方面を中心に移出された。多い時は対馬全体で年間18,000トン、炭俵120万俵を出荷。日掛周辺もそうだが、供給量を賄うために炭焼き人夫として多くの朝鮮人が雇われ、対馬中の山に入った。
戦後になると、社会生活の変化による炭離れと過酷な労働環境が原因だろうか、日掛でも炭焼きは1960年(昭和35年)頃に終了。ほとんどの人が炭焼きをやめて対州鉱山に勤めたそうだ。
対州そばの原種を求めて
2015年(平成27年)に日掛地区で作成された『日掛地区地域づくり計画書』では、「地区の現況」として、「日掛地区は、対馬の峰・有明山の麓にあり、周囲を山々に囲まれ、佐須川の上流に位置し、少ない農地には、米及びそばを作付けしている。そばに関しては、対州そばの在来種を地区内で栽培し、対州そば振興協議会により対馬全島にそのそばの種を配布し、ブランド化を図っている。人口は減少傾向で、高齢化が非常に高い状況である。(一部加筆)」と書かれてある。
そばは他品種と交雑しやすいという特徴があり、一時対馬のそばは収穫量の多い品種の導入により、在来種である対州そばが失われそうになったことがある。そこで在来種を守るべく、在来種だけで交接できるよう、日掛の山によって隔絶された環境を活かして、在来種だけを栽培するプロジェクトがスタートした。その後、対州そばは、2018年に地域ブランドとしてGI(地理的表示補償制度)登録され、多くの観光客や島民に対州そばならではの美味しさを提供している。
現在、日掛は、その対州そばの、対馬唯一の在来種栽培地として、その存在意義を高めつつある。

日掛の久田側(佐須川上流方向)

日掛の佐須側(佐須川下流方向)
対馬八十八カ所第十番札所
下原の方から村に入るとすぐに目に入るのが、きれいに草が刈られたお寺のような、神社のような空間。ここが対馬八十八カ所巡礼の第10番札所だ。
佐須側の村はずれにあり、対馬の札所としてはかなり立派な弘法大師堂には千手観世音が納められており、日掛に住んでいる篤信家が掃除や手入れを行っているという。
また、すぐ近くに11番札所と12番札所が並んで設置されており、八十八カ所巡礼では3札所を短時間で回ることができる。

手入れの行き届いた弘法大師堂境内
その他
◎日掛水源の森:有明山の南西側は佐須川の源流域(日掛川)であり、対馬林業公社が所有する「日掛水源の森」として自然環境が保護されている。
【地名の由来】 山と山に挟まれた山陰にあるので、本来は「日陰」だろうが、音はそのままにして漢字表記を「日掛」に変えたということだろう。変更理由は、「陰」と「掛」、画数は同じなので、やはり漢字の意味のイメージだろうか。
Ⓒ対馬全カタログ